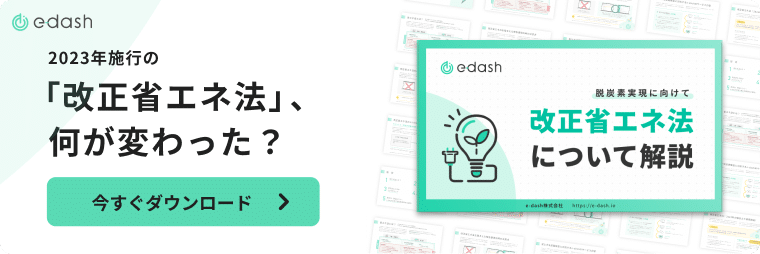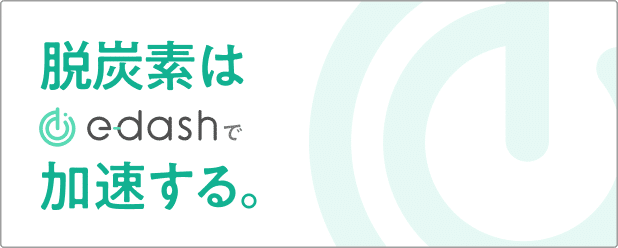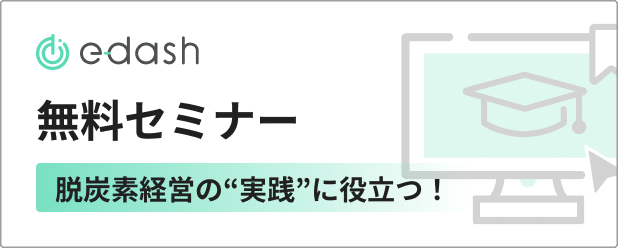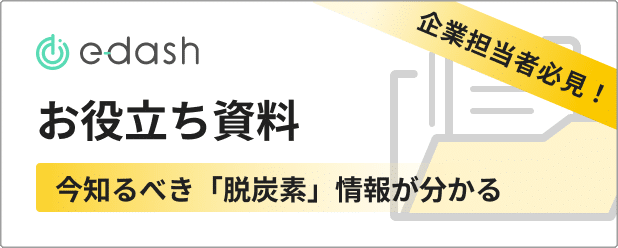SBTiとは「Science Based Targtes initiative」の略称で、科学に基づく気候目標を設定した組織・企業間のコラボレーションです。
世界各国で環境問題に対する様々な取り組みが行われていますが、国だけでなく各企業も様々な取り組みを行っており、近年注目されているSBTiに参加する日本の有名企業が増加しています。
本記事ではこのSBTiについて概要やSBTとの違い、参加するメリットなどを詳しく解説していきます。
目次
SBTiとSBTとは?わかりやすく解説
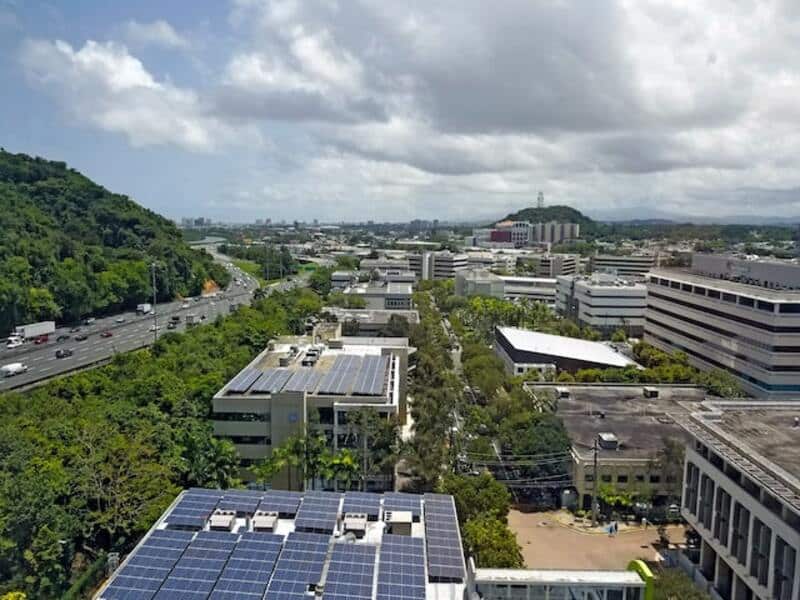
はじめに、SBTiの基本的な内容、またSBTとの違いについて解説します。
SBTiとは
SBTiとは「Science Based Targtes initiative」の略称で、科学に基づく気候目標を設定した組織・企業間のコラボレーションです。WWF(世界自然保護基金)、CDP(国際的な環境非営利団体、旧Carbon Disclosure Project)、世界資源研究所、国連グローバル・コンパクトによる共同イニシアティブの体制をとっています。
SBTiの削減目標
SBTiは企業に対して、気候変動による世界平均気温の上昇を「産業革命前と比べて、1.5℃に抑える」という目標をかかげています。
科学的知見と整合した削減目標を定めた点がSBTiの特徴です。2050年までの長期視点に基づいた温室効果ガスの削減目標など、より具体的で現実的な削減目標の設定を重視・推奨しています。
SBTiとSBTの違い
SBTとは「Science Based Targets」の略称で、パリ協定に基づいて設定された温室効果ガス排出削減目標を指します。パリ協定では、世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また1.5℃抑えることを目標としています。
また、SBTは5〜15年先を目標として企業が設定可能です。SBTiは気候目標を達成する共同イニシアティブ・コラボショーンを指すのに対して、SBTは気候目標自体を指します。SBTiのもとで、SBTが設定されます。
SBTiに参加すると得られる3つのメリット

企業がSBTiに参加することで、下記に挙げる3つのメリットが得られます。
・SBTiはESG投資を受けやすい
・パリ協定に適合する企業としてアピールできる
・ビジネスの拡大に繋がる
SBTiはESG投資を受けやすい
SBTiに参加することで、投資家からESG投資を受けやすくなります。
ESG投資とは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の3つの側面から企業を評価して投資を行うことです。企業が長期的・持続的に成長していくためには、経営においてESGの3つの観点が必要だとされています。
また、ESGの観点から企業を評価して、中長期の投資を行う機関投資家・個人投資家も増加しています。
SBTiに参加することで、環境目標に取り組んでいる企業として投資家にアピールできます。特に「環境(Environment)」「社会(Social)」の側面で貢献している企業であることを強調できます。企業価値を高める上でも、SBTiは有効活用できる取り組みとなります。
パリ協定に適合する企業としてアピールできる
SBTiに参加することで、パリ協定に適合する企業としてアピールできます。パリ協定は前述した通り、世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また1.5℃抑えることを目指す旨が規定されています。SBTiではパリ協定に基づいた環境目標が定められ、SBTiに参加すれば自動的にパリ協定にも適合する企業である。という評価を得ることができます。
ビジネスの拡大に繋がる
SBTiに参加すると、ビジネスの拡大にも繋げられます。また、SBTiに参加して企業に対するESG投資が増えればこれまで実施できなかった規模でビジネスを展開することも可能です。
さらに、SBTiに参加している企業間で、環境目標に適合した新たな製品・テクノロジーの開発を共同で行う機会も増えていきます。
SBTiは必ずしも営利目標を含んだイニシアティブではありませんが、環境目標の遂行が間接的に企業へ利益をもたらす可能性が高いです。
SBTiに参加している企業を紹介!

それでは実際にSBTiに参加している企業について確認していきましょう。
SBTiに参加している日本企業は200社以上
2022年8月1日現在、SBTiに参加している日本企業は200社を超えています。
下記は、日本のSBT認定企業の一例です。
業種:建設業のSBT認定企業
清水建設、住友林業、積水ハウス、大東建託、大成建設、大和ハウス工業、東急建設、長谷工コーポレーション、前田建設工業、LIXILグループ
業種:食料品のSBT認定企業
アサヒグループホールディングス、味の素、カゴメ、キリンホールディングス、サントリー食品インターナショナル、日清食品ホールディングス、日本たばこ産業、明治ホールディングス、ロッテ
業種:繊維製品のSBT認定企業
帝人
業種:化学のSBT認定企業
花王、コーセー、資生堂、住友化学、積水化学工業、ユニ・チャーム、ライオン
業種:医薬品のSBT認定企業
アステラス製薬、エーザイ、大塚製薬、小野薬品工業、参天製薬、塩野義製薬、第一三共、武田薬品工業、中外製薬
業種:金属製品のSBT認定企業
YKK AP
業種:ガラス・土石製品のSBT認定企業
TOTO、日本板硝子、日本特殊陶業
業種:非鉄金属のSBT認定企業
住友電気工業、古河電機工業、YKK
業種:機械のSBT認定企業
小松製作所、DMG森精機、日立建機
業種:電気機器のSBT認定企業
オムロン、カシオ計算機、京セラ、コニカミノルタ、シャープ、セイコーエプソン、ソニー、東芝、日本電気、パナソニック、日立製作所、富士通、富士フィルムホールディングス、ブラザー工業、三菱電機、村田製作所、ヤマハ、リコー、ローム
業種:輸送用機器のSBT認定企業
日産自動車
業種:精密機器のSBT認定企業
島津製作所、ニコン
業種:印刷のSBT認定企業
大日本印刷、凸版印刷
業種:海運業のSBT認定企業
川崎汽船、日本郵船
業種:情報・通信業のSBT認定企業
エヌ・ティ・ティ・データ、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、日本電信電話、野村総合研究所
業種:小売のSBT認定企業
アスクル、イオン、ファーストリテイリング、ファミリーマート、丸井グループ
業種:不動産業のSBT認定企業
東急不動産ホールディングス、東京建物、野村不動産ホールディングス、三井不動産、三菱地所
業種:サービス業のSBT認定企業
セコム、電通、ベネッセコーポレーション
日本の名だたる大企業がSBTiに参加しています。
上記で挙げた大企業以外にも日本の多くの中小企業がSBTiに参加しており、今後もSBTiに参加する日本企業が増加すると予想されます。
SBTiに加盟している企業は世界で1,000社以上
2020年10月に、SBTiに加盟して意欲的な削減目標にコミットした企業が世界で1,000社を超え、2023年3月に2,310社になりました。
企業名を記載すると膨大な数になりますので今回は記載を控えますが、世界各国のグローバル企業の多くがSBTiに参加している状態です。
世界的には、専門サービス業・食料品製造業・不動産業の企業の参加が多く見られます。
日本では電気機器・化学メーカー企業の参加が多いですが、世界では非製造業の分野でSBTiに対する関心が高いことが伺えます。
SBTiの目標設定の方法は?SBTiの基準も解説!

次に、SBTiの目標設定の方法、SBTiの基準、SBT申請の流れについて解説します。
SBTの考え方を知っておこう
SBTiの目標設定を行う際は、SBTの考え方に基づいて目標を定める必要があります。SBTの考え方にそった目標設定になっていない場合、後のSBT申請の審査に落ちてしまう可能性があるので確認しながら行ってください。
SBTの削減目標設定は、下記の考え方が基本になります。
・Scope1, 2及びScope3(該当うる場合)について目標設定の必要がある
・Scope1, 2の目標は、セクター共通の水準としては「総量同僚」削減とする必要がある
・Scope3の目標は、以下のいずれかを満たす「野心的な」目標を設定する
(総量削減か原単位削減、あるいはサプライヤー/顧客エンゲージメント目標)
・事業セクターによっては、セクターの特性を踏まえた算定手法も容易されている
※Scopeとは
Scope1:事業者による温室効果ガスの直接排出
Scope2:他社供給による電気・熱・蒸気の使用に伴う温室効果ガスの関節排出
Scope3:Scope1, 2以外の温室効果ガスの関節排出
<SBTの基本的な削減経路>
①目標水準と設定手法を選択
②削減経路を算出
③SBT目標年を提出年より5年~10年の範囲から選択
④目標値の決定
SBT設定で適用される基準の概要は下記の通りです。
・バウンダリ(範囲):企業全体(子会社含む)のScope1及び2をカバーする、すべての関連するGHG(温室効果ガス)が対象
・基準年・目標年:基準年はデータが存在する最新年とすることを推奨(未来の年を設定することは認められていない)
目標年は申請時から「最短5年、最長10年以内」
・目標水準:最低でも世界の気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃以内に抑える削減目標を定める必要がある。
→SBT事務局が認定するSBT手法に基づき目標設定
→総量同量削減の場合は「毎年4.2%削減」
Scopeを複数合算(たとえば、1+2または1+2+3)した目標設定が可能。ただし、Scope1+2及びScope3でSBT水準を満たすことが前提
他社のクレジット取得による削減、もしくは削減貢献量はSBT達成のための削減に算入できない
SBT申請の流れ
SBTの申請は下記の流れに沿って進めていきます。
①【任意】Commitment Letterを事務局に提出
・「コミット」とは、2年以内にSBT設定を行うという宣言のこと
・コミットした場合はSBT事務局、CDP、WMBのWebサイトにて公表される
②目標を定め、申請書を事務局に提出
・Target Submission Formを事務局に提出して、審査日をSBTi booking systemで予約
③SBT事務局による目標の妥当性確認・回答(有料)
・事務局は認定基準への該否を審査し、メールで回答(否定する場合は、理由も含む)
・目標の妥当性確認には「USD 9,500(外税)」の申請費用が必要(最大2回の目標評価を受けられる)
・以降の目標再提出は、1回につき「USD 4,750(外税)」の申請費用が必要
④認定された場合は、SBT等のWebサイトにて公表
⑤排出量と対策の進捗状況を1年に1回報告し、開示
⑥定期的に、目標の妥当性の確認
・大きな変化が生じた場合は、必要に応じて目標を再設定(少なくとも5年に1度は再評価)
SBTの申請は上記の流れに沿って進んでいきます。即日でSBTiに参加できる訳ではないので注意してください。
SBT ネットゼロ(Net-Zero)とは?SBTiとの関係を解説!

SBTiに参加する前に合わせて把握しておきたいのが「SBT ネットゼロ(Net-Zero)」という考え方です。ここでは、SBT Net-Zeroと認定取得済企業数について解説します。
SBT ネットゼロ(Net-Zero)について
SBT Net-Zeroとは、SBTiにおけるネットゼロの考え方です。ネットゼロとは、温室効果ガスまたは二酸化炭素の排出量から吸収量・除去量を差し引いた合計値をゼロにするという意味です。ネットゼロの考え方自体は様々な環境目標値において利用されていますが、SBTiにおいてネットゼロの考え方を取り入れたのがSBT Net-Zeroになります。
SBT Net-Zeroにおいては、1.5℃水準の削減目標(Near-term SBT、Long-term SBT)を設定して、残余排出量と炭素除去を釣り合わせることが求められます。SBT Net-Zeroを設定することで、SBTの実現をより具体的に進められます。
SBT Net-Zero認定取得済みの日本企業
SBT Net-Zeroの認定は通常のSBTiよりも規定が厳しいです。そのため、SBT Net-Zeroの認定を取得している企業は世界で42社にとどまっています。
日本企業は、三菱地所と日本ゼルスの2社のみ、SBT Net-Zeroの認定を取得している状態です。
ただし、SBT Net-Zeroにコミットしている企業は世界で1,305社となっています。このうち、日本企業の数は41社です。
今後コミットしている企業が正式にSBT Net-Zeroに認可されればSBT Net-Zeroはよりスタンダードなネットゼロ基準になると思われます。
SBTiに参加してみよう

SBTiに参加することで、気候問題への取り組みを内外に広くアピールすることが可能です。機関投資家・個人投資家からのESG投資を増やせるきっかけにもなります。
SBTiに参加するためには、GSGの具体的な削減目標が不可欠です。感覚的にGSGの削減目標を定めるのではなく、定量的に数値目標を設定する必要があります。
そこでぜひ活用していただきたいのが「e-dash」です。e-dashは、GSG排出量削減への取り組みを総合的にサポートするサービスプラットフォームになります。

e-dashでは、請求書をスキャンしてアップロードするだけで、CO2排出量の自動算出と分析を行うことができます。
CO2排出量削減への目標設定やロードマップの作成も可能となっており、排出量のデータ報告や対外公表をスムーズに進めることができます。
現在、e-dashは無料で利用できるデモタイプを提供しています。これを機にe-dashを試して頂きぜひSBTi申請への活用にお使い下さい。