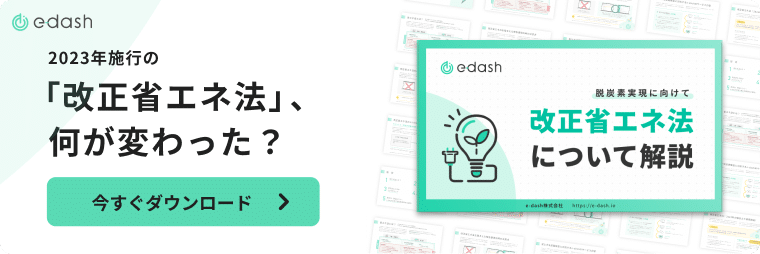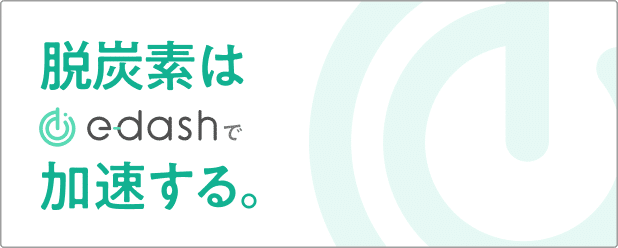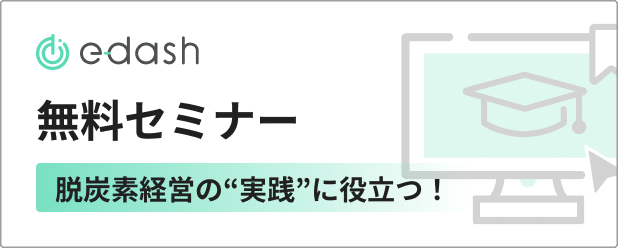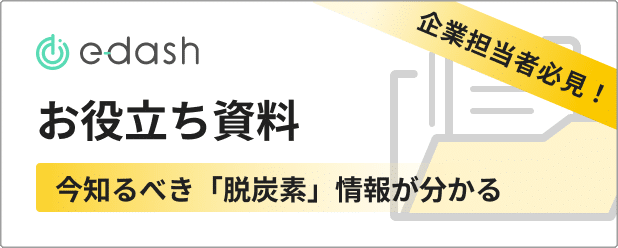2015年に採択されたSDGs17の目標は、テレビや雑誌で大きく取り上げられるようになり、高校教育で取り入れられる機会も年々増加しています。しかし、SDGSというと企業が行う物と思われがちで身近に感じ辛いかも知れません。そこで今回は、企業だけでなく高校生によるSDGsの取組事例を6つほどご紹介します。
また、身近な例を通じて、私たちにもすぐに始められる7つのSDGs活動についても記載致します。ぜひ最後までご覧ください。
目次
SDGsとは?

SDGsは「Sustainable Development Goals」を略したもので、日本語では「持続可能な開発目標」と呼びます。
2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットで構成され、先進国だけではなく発展途上国を含む共通の目標として、積極的に取り組まれています。
では、17の目標を簡潔にみていきましょう。
| No. | 目標 | テーマ |
| 1 | 貧困をなくそう | あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる |
| 2 | 飢餓をゼロに | 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する |
| 3 | すべての人に健康と福祉を | あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する |
| 4 | 質の高い教育をみんなに | すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する |
| 5 | ジェンダー平等を実現しよう | ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う |
| 6 | 安全な水とトイレを世界中に | すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する |
| 7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する |
| 8 | 働きがいも経済成長も | 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する |
| 9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る |
| 10 | 人や国の不平等をなくそう | 各国内及び各国間の不平等を是正する |
| 11 | 住み続けられるまちづくりを | 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する |
| 12 | つくる責任 つかう責任 | 持続可能な生産消費形態を確保する |
| 13 | 気候変動に具体的な対策を | 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる |
| 14 | 海の豊かさを守ろう | 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する |
| 15 | 陸の豊かさも守ろう | 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する |
| 16 | 平和と公平をすべての人に | 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する |
| 17 | パートナーシップで目標を達成しよう | 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する |
1〜6は発展途上国向けの目標で、7〜13はすべての国に当てはまる目標です。
【関連記事】SDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」を徹底解説
SDGsについて高校生が行った取組事例

SDGsは世界規模で掲げている目標ですが、小中学生や高校生も積極的に取り組んでいます。今回は全国の高校生が実際に行った取り組み事例について、「SDGsのどのゴールに関係する取り組みをしたのか」や「取り組み内容」を紹介します。
紹介する高校は以下の3校です。
- 川村高等学校(東京都)
- お茶の水女子大学附属高等学校(東京都)
- 聖徳学園高等学校(岐阜県)
川村高等学校(東京都)
川村高等学校では3年生が国連開発計画(UNDP)を訪問し、近藤哲生UNDP駐在代表から話を聞き、国連大学内の施設を見学する校外授業を行いました。活動は以下のとおりです。
【目的】持続可能な開発目標(SDGs)を含む国際問題についての理解を深める
【取組内容】国連大学の施設を見学。近藤哲生氏に質疑応答をする
【どのゴールに関係する取り組みか】すべての取り組み(全体像の把握)
【成果】SDGsを含めた国際問題に対する理解と認識を深められた
SDGsとUNDPの取組み方の違いを把握できた
※UNDPは国連の開発ネットワークを先導する機関で、世界の170カ国以上の国で活動し、開発途上国がその開発目標を達成できるように支援しています。
お茶の水女子大学附属高等学校(東京都)
お茶の水女子大学附属高等学校では国連SDGs達成のための世界におけるジェンダー啓発イベント「What is GENDER?‐未来を作るのは私たち‐」を開催しました。活動は以下のとおりです。
【目的】SDGs啓発
【取り組み内容】発展途上国の女子の現状とジェンダー啓発動画上映・有識者ミニトーク
【どのゴールに関係する取り組みか】5.ジェンダー平等を実現しよう
【成果】幅広い年齢層の参加者があり、課題に対する理解の広がり、深まりがみられた。
お茶の水女子大学附属高等学校では、ジェンダー平等や女性の社会進出について大学のジェンダー研究所や国連OGOB団体との連携も推進されており、JPXと朝日新聞主催の高校生ビジネスプラン発表会で最優秀賞も受賞している学校です。
聖徳学園高等学校(岐阜県)
聖徳学園高等学校では高校2年生の総合学習の時間で行うPBL型学習を行っています。各クラスで異なる発展途上国を担当し、1年かけて担当国の問題の発見から解決までを行う授業です。
【目的】担当国に対する理解とSDGsに対する理解を深める
【取り組み内容】各クラスごとに発展途上国を決め、その国の問題解決の提案と実行をする【どのゴールに関係する取り組みか】1〜6の目標
【成果】
- 見知らぬ場所に住む人々が抱える問題の積極的な解決方法を提案する力を養える
- SDGsの目的達成のために「私たちができることは何なのか」主体を学べる
- 個々の教科で学んだ知識を統合し創造できる1年かけて発展途上国の現状や問題点を話し合い、最終的に貢献成果物を現地に届けることもある実践授業を通じ、SDGsに対し主体的に行動する力が身に付けます。
1年かけて発展途上国の現状や問題点を話し合い、最終的に貢献成果物を現地に届けることもある大きなプロジェクトで、SDGsに対し主体的に行動する力が身に付く実践授業です。
【関連記事】カーボンニュートラルへの企業の取り組みとは?注目される背景や進め方をわかりやすく解説!
高校が行っているSDGsへの取組事例

前述では高校生が主体になっている高校をピックアップしましたが、高校としてSDGsに取り組んでいる学校もあります。学校によって異なる教育方法を取り入れており、楽しみながら行える事例も少なくありません。ぜひ参考にしてみてください。
高校は以下のとおりです。
- 武田高校(広島県)
- 光ヶ丘女子高校(東京都)
- 御殿場西高等学校(静岡県)
武田高校(広島県)
武田高校は1967年に創立された学校です。「世界的視野に立つ国際人の育成」を校風に掲げており、SDGs達成に向けた実践校となることを宣言しています。活動内容は以下のとおりです。
・SDGsカードゲーム2030(SDGs Week)
全校生徒が1週間かけて世界の現状からわたしたちにできることを考えるゲームを行い、生徒たちが持続可能な社会の実現に向けてSDGsの取り組みへのものさしを手に入れる授業です。
・横断型授業
高校1年生に向けて行われている授業では、現代文・保健・家庭科・英語の4つの教科で、食品ロス、貧困、健康的な食事、途上国、災害時に必要とされている食について身近な例に加え様々な角度から学びます。
・高校総合学習
高校1年生と2年生がそれぞれの探求学習を行います。
グループごとに17のゴールに関わる課題の設定を行う。1年生は「広島」2年生は「アジアと日本」をテーマにし、現代社会の問題と解決策を考える授業です。
・生徒によるプロジェクト
ペットボトルを回収しエコキャップアートを作成・クラスTシャツをフェアトレードの製品で作成・子ども服を回収しUNIQLOの企画に参加するなど、身近な例を題材とした生徒発案のプロジェクトも多く存在します。
光ヶ丘女子高校(東京都)
光ヶ丘女子高校は、内閣府の「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」のメンバーとして登録されています。光ヶ丘女子高校の活動内容は以下のとおりです。
・教育学習×SDGs
すべての教科の学びをSDGsとつなげており、例えば国際教養科ではSDGsの視点で分析したものを英語でプレゼンテーションするような授業を行っています。
・クラブ活動×SDGs
運動部では、心身の健康やフェアプレー精神など公平・公正・平等などの価値観を養い、文化部では音楽や芸術を通して資源問題や平和について考えています。他に生徒会では「わたしたちにできること」をモットーに寄付活動やリサイクル活動を行っています。
・学校行事×SDGs
文化祭では食物バザーや研究発表、研修旅行ではSDGsの17の目標に基づいたプロジェクトについて学ぶ機会を設け、奉仕活動も積極的に行っています。
御殿場西高等学校(静岡県)
2020年度からSDGsを推進し始め、SDGs委員会のある御殿場西高等学校。生徒一人ひとりが当事者意識を持ち、主体的な活動をしています。活動内容は以下のとおりです。
・SDGs委員会
各クラスから選出されたメンバーが学年の枠を超えて各月毎にSDGsアクションを起こしていくことを目標として活動しています。
・SDGsステッカーを全教室へ
生徒の目にいつでも止まるようにホワイトボードにはステッカーが用意されています。教科にかかわらず様々な単元とSDGsを組み合わせ、意識づけを行っているのも特徴的です。
・授業内でのSDGs教育
特進・進学コースの英語学習や総合的な探求の時間などでSDGsについて学びます。学校における様々な課題をSDGsの枠組みのなかで考え、解決策を見つけていき、生徒から提案があったものは次年度の学校運営で反映されるという体制が敷かれています。
教育現場で行われているSDGsへの取組事例

教育現場で行われている取り組みとして、教師や学校向けに開かれたセミナーやプログラムもあります。
特に、教師は生徒に教えるためにも自身がしっかりと知識を身につけなければなりません。
また、セミナーなどを学校でも積極的に活用する事で、SDGsにおける生徒の知識幅はきっと広がるでしょう。
下記でおすすめのセミナーやプログラムをご紹介しますので参考にしてみて下さい。
1.菅公学生服(株)によるSDGsセミナー
「SDGsとは何か」「身近なところから私たちができることは何か」など基本的なところから学習できるセミナーです。
具体的には第一章では「SDGsとは何か」第二章では「第2章.制服・体操服とSDGsについて」第三章では「わたしたちができることは何か」について行われます。
特にSDGsの基礎的内容やトランスジェンダーと制服との関わりについて、知識を深めるのに適したセミナーです。
2.文部科学省主催のオンラインセミナー
文部科学省では定期的に教師向けにSDGsに関するオンラインセミナーが開催されています。
SDGs中の17個の目標だけでなく、その下にある「ターゲット」についてや、生まれた背景などについても詳しく学べます。
また、学校でのSDGs学習の際に、留意しなければならないポイントなども知ることができます。
オンラインなので、忙しい方でも気軽に受けられるのが嬉しいところ。
生徒に何を伝えたらよいのか迷ったら参考にすると良いでしょう。
高校生のSDGsへの取り組みに企業が協力した事例

高校生と企業が協力してSDGsに取り組む事は、目標達成した未来へと導くため重要な事です。
なぜなら、高校生と企業のコラボによる取り組みは、学生の教育とキャリアの発展を促進し、同時に企業の社会的責任を果たすことに繋がるからです。
高校生の取り組みに対し、企業が協力した事例をいくつかあげていきます。
イノベーションコンテスト
企業が主催する高校を対象とした「SDGsイノベーションコンテスト」などもあります。
これは、学生がSDGsに関連する新しいアイデアや解決策を企業の前で発表するコンテストです。
企業は優れた企画に対し賞金を出すだけでなく、実際にアイディアを取り入れ製品化する事も。これを授業の一環として取り組んでいる学校もあります。
インターンシップとメンターシッププログラム
企業が高校生に対してSDGsに関連するインターンシッププログラムやメンターシッププログラムを提供している事例もあります。
これに参加する事により、学生は実際のビジネス環境でSDGsに取り組む方法を学ぶ事ができます。
▼SDGsにおける企業の取り組みに関してもっと詳しく知りたい方は下記をご覧下さい!
高校生活のなかでできる、SDGsの7つの取り組み

SDGsの目標は幅広く、私たちの生活と密接しています。いつもの行動を少しだけ改めるだけでもSDGsに貢献できるため、実践してみましょう。
ここでは、簡単に取り組める身近な例を7つご紹介します。
- 物を大切に使う
- 水や電気をこまめに止める
- 認証マーク入りの商品を選ぶ
- マイバッグを持ち歩く
- マイボトルを使う
- 差別や偏見をなくすよう意識する
- SDGsへの理解を深める
1. 物を大切に使う
物を大切に使うことは、SDGsの目標12である「つくる責任 つかう責任」に含まれます。
食品や勉強道具・洋服・日用品など、普段使うものの浪費が持続的開発を阻む要因の一つにもなるため、一人ひとりが廃棄物を減らし、リユースを行うことが不可欠です。
そのため、部活用品や文房具など、日常的に使う物を大切に扱い、壊れたらなるべく修理して使うようにすると良いでしょう。
2. 水や電気をこまめに止める
普段何気なく使っている電気や水は、作られてから使うまでに多くのエネルギーを使い、温室効果ガスが排出されます。温室効果ガスは地球温暖化の要因とも言われており、削減すべきものです。
そのため、水を出しっぱなしにしない、使っていない部屋の電気を消すなど、節水や節電を心がけるようにしましょう。
3. 認証マーク入りの商品を選ぶ
認証マークは、商品やサービスを差別化するために使用され、商品やサービスの品質・性能・安全性を証明しています。例えば、以下のような認証マークがある商品やサービスを選ぶと、SDGsに協力することになるでしょう。
- 環境にやさしい森林認証制度を「FSC認証」
- 水産資源と環境に配慮したエコラベル「MSC認証」
- 環境と社会への影響を最小限にした責任ある養殖の水産物の証「ASC認証」
- 国際フェアトレード基準を満たす商品「国際フェアトレード認証ラベル(複数あり)」
- 古紙を再生して作られた商品「グリーンマーク」
- 世界中で同じ品質を提供する認証制度「ISO認証」
- 認証マークは、商品だけでなく企業の品質管理にも採用されています。
4. マイバッグを持ち歩く
エコバッグを持ち歩くことでレジ袋に使われるプラスチックを減らすことにつながります。SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」では、海の環境や生き物を守るために海洋プラスチックの削減が必要です。
海に流れ込むプラスチックごみは年間500〜1300万トンと言われており、2050年には海で暮らす魚の量よりも、海に漂うプラスチックごみの量の方が多くなるとも言われています。
身の回りにはプラスチック製品があふれていますが、まず私たちにできることはマイバッグを使い、レジ袋の削減に協力することでしょう。
5. マイボトルを使う
コンビニや自動販売機で気軽に飲み物が買えるのは便利ですが、マイボトルを使うことでプラスチックの削減やエネルギー消費の抑制が可能です。ペットボトルはリサイクルして再利用できるものの、その過程でも多くのエネルギーを使いコストもかかります。また、ポイ捨てされたペットボトルが海に流れ着き、海洋生物にも影響を与えていることも大きな問題です。
マイボトルを使えばペットボトル飲料を購入する必要がなくなり、プラスチックの削減だけでなくお金の節約にもなります。
6. 差別や偏見をなくすよう意識する
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」に含まれる男女差別やジェンダーマイノリティへの偏見問題は、世界だけではなく日本でも起こっています。
高校のクラスや学校のなかで、いじめや偏見はありませんか?自分と違うからと相手を否定するのではなく、まずはその人を理解することから始めてみましょう。また、いじめをしないことはもちろん、見て見ぬふりをせずに止める勇気も必要です。
7. SDGsへの理解を深める
SDGsに掲げられている17の課題は、決して特別なことではありません。私たちにできることもたくさんあります。
SDGsに関する取り組みは一人でも始められますが、課題を解決していくにはより多くの人に理解してもらうことが重要です。そのため、身近な例として世界や社会で問題となっている点を友人と話し合ってみる、SNSで情報収集・発信するなど、周囲の人を巻き込んでいくのがおすすめです。
2022年の日本の目標達成度は19位となっており、前年度を下回る結果となりました。私たちにできることはまず、SDGsへの理解を深め身近なことから一人ひとりが意識し行動することです。そうすることで、きっと順位も改善していくでしょう。
高校生のSDGsへの取組事例を参考に、私たちにできることから始めよう!

高校生のSDGsへの取組事例を全部で6つ紹介しましたが、どの学校も個性的で学校行事や授業の中に密に取り入れていました。
2030年までにSDGs17の目標を達成するには、国や企業だけが参加するのではなく、私たち一人ひとりが意識して取り組まなければなりません。
「マイボトルやマイバッグを持ち歩く」「人種差別やジェンダーマイノリティーへの偏見をなくす」「水や電気をこまめに消す」など、高校生でも普段の生活のなかで簡単に始められることばかりです。まずは、そういった身近な例を参考に私たちに自分にできることから始めてみてください。