
「自社のCO2排出量をどうやって計算すればいいの?」と疑問を持つ担当者は多いのではないでしょうか。CO2排出量を計算するには、電力使用量や燃料使用量などのデータを整理し、公式の排出係数を用いる必要があります。本記事では、算定手順や注意点、削減に向けた具体的な取り組みや可視化のメリットを解説します。
目次
CO2排出量の計算が求められる背景

CO2排出量の計算が求められる背景には、地球温暖化や気候変動に対する国際的な流れと、それらを踏まえた日本国内の動きがあります。CO2排出量の算定と削減は、大企業に限らず中小事業者にも広く関わる重要な課題です。ここでは、国内外の動向について解説します。
国際的な動向
地球温暖化や気候変動への対応が国際的な急務となるなか、CO2排出量の正確な計算と報告は、企業にとって不可欠な要素となっています。
その大きな契機となったのが、2015年に採択され2016年に発効した「パリ協定」です。この国際的な枠組みを背景に、世界各国は脱炭素社会に向けた施策を本格化させています。このような潮流のなか、ESG投資が急速に拡大しており、環境情報の開示が投資家や金融機関による企業評価に直結するようになりました。
さらに、企業は国際的なイニシアチブへの対応も強く求められています。具体的には、科学的根拠に基づく削減目標の設定を求めるSBTiや、排出量と気候リスクの公開を促すCDP、気候関連リスク・機会の情報開示を進めるTCFDなどです。
グローバル企業との取引や資金調達を円滑に進めるためには、これらの国際的な要求に応える信頼性の高い算定と報告体制を整備することが欠かせません。
国内の動向
国際的な脱炭素化の潮流に加え、国内制度の強化も企業のCO2排出量算定を後押ししています。
日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、一定規模以上の事業者は省エネ法や温対法により排出量の算定・報告が義務づけられました。また、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)による基準整備も進み、開示の重要性が一層増しています。
さらに、大企業がサプライチェーン全体でカーボンニュートラルを目指すなか、取引先に算定結果の提出を求める動きも拡大中です。こうした流れへの対応は、単なる規制遵守にとどまらず、事業継続やコスト削減、競争力強化の基盤にもつながります。
CO2排出量を計算する際の対象範囲
CO2排出量の計算には、事業単位で算出する方法と製品単位で算出する方法があります。企業は、目的に応じてこれらの手法を使い分けることが求められるでしょう。
サプライチェーン排出量(Scope 1, 2, 3)
サプライチェーン排出量は、企業活動に伴って排出されるCO2などの温室効果ガス排出量の全体像を指します。実際に計算する際は、直接排出と間接排出に分けるのが基本です。具体的には、排出源に応じて以下のScope 1から3に分類して計算を進めます。
| Scopeとは? Scope 1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセスなど) Scope 2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 Scope 3 : Scope 1、Scope 2以外の間接排出(調達、物流、製品使用、廃棄など事業者の活動に関連する他社の排出) |
これらの範囲を網羅することで、企業の排出量削減目標を具体的な数値で示せるようになり、取引先を含めた排出リスクの全体像を把握できるようになります。
製品単位排出量(カーボンフットプリント)
製品やサービスの原材料調達から生産、流通、使用、維持管理、廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通じて排出されるGHG排出量をCO2換算して算定する方法です。この方法は一般的に、カーボンフットプリント(CFP)と呼ばれています。
CFP算定の目的は、製品ごとの環境負荷を「見える化」することにあります。消費者が環境に配慮した製品を選ぶ際の判断基準となるだけでなく、企業が製品の設計や製造プロセスを改善し、より環境に優しい製品を開発するための指標としても活用することが可能です。
CO2排出量の計算方法

環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」を基に作成
CO2排出量は基本的に「活動量 × 排出係数」で算定します。活動量とは燃料使用量や電力消費量などの実績値を指し、排出係数はそれぞれの使用に伴うCO2排出の割合を示すものです。
企業単位の算定では、Scope 1~3を対象に、燃料や電力の使用量、廃棄物の排出量などの活動データに基づいて算出します。
一方、製品単位の算定は、原材料調達から製造、流通、使用、廃棄までを対象に、投入資材の量や製造プロセス、輸送距離、使用条件など細かいデータを収集します。
排出係数は環境省やIPCCが公表しているものを算定目的に応じて選び、活動量は電気料金明細や燃料購入記録などから把握可能です。
活動量とは
CO2排出量は、企業における活動量によって大きく変わってきます。この活動量とは、以下のように定義することができます。
| 活動量とは、事業者の活動の規模に関する量のこと 例)電気使用量、貨物輸送量、廃棄物処理量など |
一般に、企業の事業規模が大きくなるほど、それに比例して活動量も増加する傾向があり、結果としてCO2排出量も増える可能性があります。
排出係数とは
排出係数もCO2排出量算定の算定に必要な項目です。排出係数については、以下のように定義することができます。
| 排出係数(排出原単位)とは、一単位あたりの活動量がもととなり排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの量のこと |
国内において、企業が自社で算定したデータや他社が算定したデータを排出係数の一次データとして定義することができますが、二次データとして以下のデータベースなどで定義される排出係数を活用することも可能です。
① 環境省HPに掲載されている温対法算定・報告・公表制度における排出係数
これらの排出係数は種類が多く、適切なものを選ぶには専門的な理解が必要です。特にScope 2の算定では、基礎排出係数と調整後排出係数の2種類を正しく使い分けることが重要です。
| 1.基礎排出係数 基礎排出係数=(販売した電気の発電時に燃料から排出されたCO2量 − 非化石証書・グリーン電力証書・再エネ由来クレジットによる削減量)÷ 販売電力量(kWh) |
| 2.調整後排出係数 調整後排出係数=(基礎排出係数に基づくCO2排出量 − J-クレジットやJCMクレジットなどによるカーボンオフセット量)÷ 販売電力量(kWh) |
CO2排出量を計算する流れ
| 1. 算定の目的を明確にする 2. CO2排出源を洗い出す 3. 必要なデータを収集する 4. CO2排出量を計算・集計する |
CO2排出量の計算は、まず算定の目的を明確にし、対象範囲や精度の方針を定めることが重要です。算定目的を踏まえ、自社の事業活動でCO2を生み出す要因を特定し、排出源ごとに燃料や電力使用量など活動量のデータを収集します。
サプライチェーン排出量の計算方法
サプライチェーン排出量は、企業が直接・間接的に関与する温室効果ガス排出量を合算したもので、以下の式で表されます。
| サプライチェーン排出量 = Scope 1排出量 + Scope 2排出量 + Scope 3排出量 |
Scope 1:自社の燃料燃焼や工場設備からの直接排出
| 算定式:活動量(燃料使用量) × 排出係数 |
Scope 2:他社から供給された電気・熱・蒸気の使用による間接排出
| 算定式:活動量(電力・熱・蒸気使用量) × 排出係数(基礎/調整後) |
Scope 3:原材料の調達、物流、製品の使用・廃棄など、サプライチェーン全体に伴うその他の間接排出
| 算定式:活動量 × 排出係数(15カテゴリごとに整理) |
Scope 3は特に算定が複雑で、サプライヤーや顧客との協力が不可欠です。こうしてScope 1〜3を網羅的に算定・合算することで、企業全体のサプライチェーン排出量を把握できます。
CO2排出量を計算するときの注意点
| ・Scopeの正確な分類と把握 ・データの信頼性と一貫性の確保 ・最新の排出係数・制度への対応 |
CO2排出量を算定する際は、まずScopeの正確な分類と把握が重要です。とくにScope 3はサプライチェーン全体に関わり、従業員の通勤、製品の使用・廃棄など広範囲に及ぶため、もれが無いよう注意しましょう。
また、活動量や排出係数などのデータの信頼性と一貫性を確保することが必要です。複数拠点や部門でのデータ収集方法を統一し、トレーサビリティを維持することで算定精度が高まります。
さらに、環境省やIPCCが公表する最新の排出係数や制度改正を反映させることで、常に正確で適切な算定結果を得られます。
CO2排出量の計算における課題
| ・データの収集・管理に労力がかかる ・社内調整が必要 ・精度を維持するのが難しい |
CO2排出量の算定には、データ収集や管理に相応のリソースが必要です。とくにScope 3では、取引先や物流、製品使用など社外が保有するデータを収集するため労力がかかります。
さらに、算定範囲や精度の設定について社内調整の時間を要し、広範囲にわたる計算では精度の維持が難しい場合もあります。
Scope 3は15カテゴリと範囲が広く、データ欠損や推計が生じやすいため、精度を一定に保つことが難しい場合があります。こうした課題を解決するには、データ収集の効率化や重点カテゴリに絞った算定方針の策定が不可欠です。
CO2排出量の削減への具体的な取り組み
CO2排出量の可視化は、実効性のある削減対策へとつながります。現状を数値で把握することで排出源を特定しやすくなり、効果的な対策の立案が可能です。ここではScopeごとの具体的な取り組みについて解説します。
Scope 1での対策
まず、自社で取り組むのは「Scope 1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)」です。
Scope 1は、自らの会社運営に係る直接的なCO2排出量の削減のため取り組みやすい部分です。たとえば、自社工場で排出されるCO2などが対象となり、対策には、以下のようなものがあります。
| ・燃料を電気や都市ガスへ切り替える ・各設備の熱排出を再利用していく ・各設備を省エネ設備へ切り替える |
Scope 2での対策
次に着手しやすいのが、「Scope 2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出」です。間接排出とは、自社が購入している電気などの排出量を下げる方法です。電気・熱・蒸気などの購入エネルギーが対象になります。
Scope 2 に着目した排出量削減の対策には、
| ・購入する電力を再エネ由来の電力へ切り替える ・購入する電力だけに頼らず自家消費型太陽光発電などを利用する ・購入する電力量を減らすよう省エネ施策を実行する |
などがあります。
Scope 3での対策
対策を講じる際に大変なのが、Scope 3です。
Scope 1や2のように自社のみで対策を取ることはできず、自社以外のサプライチェーンによる排出量削減になります。
Scope 3は15つのカテゴリに分類され施策を講じていきます。
| No | Scope 3 カテゴリ | 該当する活動(例) |
|---|---|---|
| 1 | 購入した製品・サービス | 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達 |
| 2 | 資本財 | 生産設備の増設(数年にわたり建設・製造されている場合には、建設・製造が終了した最終年に計上) |
| 3 | Scope 1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等) 調達している電力の上流工程(発電に使用する燃料の採掘、精製等) |
| 4 | 輸送、配送(上流) | 調達物流、横持物流、出荷物流(自社が荷主) |
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 廃棄物(有価のものは除く)の自社以外での輸送(※1)、処理 |
| 6 | 出張 | 従業員の出張 |
| 7 | 雇用者の通勤 | 従業員の通勤 |
| 8 | リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の稼働 |
| 9 | 輸送、配送(下流) | 出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)、倉庫での保管、小売店での販売 |
| 10 | 販売した製品の加工 | 事業者による中間製品の加工 |
| 11 | 販売した製品の使用 | 使用者による製品の使用 |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 使用者による製品の廃棄時の輸送(※2)、処理 |
| 13 | リース資産(下流) | 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の稼働 |
| 14 | フランチャイズ | 自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope 1,2 に該当する活動 |
| 15 | 投資 | 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用 |
| その他 | 従業員や消費者の日常生活 |
CO2排出量の可視化が企業にもたらすメリット
CO2の排出量を可視化すると、企業にさまざまなメリットをもたらします。それぞれ詳しく見ていきましょう。
CO2削減のヒントが得られる
CO2排出量の可視化は、削減を始めるための重要な第一歩です。数値を基に現状を正確に把握することで、排出が多い具体的な発生源(工程やカテゴリ)を特定し、最も効果の高い対策を講じるための戦略的なヒントが得られます。可視化は、単に義務的な報告に対応するだけでなく、実効性のある脱炭素経営を推進することにつながるでしょう。
サステナビリティレポートへの活用
CO2排出量の定量データは、サステナビリティレポートの信頼性を高める重要な要素です。国際的な開示基準(TCFDやCDPなど)にも対応しやすくなり、企業の環境対応を客観的に示す資料として活用できます。
取引先・投資家への信頼性向上
排出量の可視化は、ESG投資やサプライチェーン管理において信頼性の証となります。取引先からの環境情報開示要求や、投資家の非財務評価に対応することで、選ばれる企業としての競争力を高められます。
経営戦略との統合(カーボンニュートラル目標)
CO2排出量の見える化は、カーボンニュートラル目標の進捗管理に不可欠です。部門別・工程別の排出量を把握することで、削減施策の優先順位や投資判断に活用でき、環境対応を経営戦略に組み込むことが可能になります。
CO2排出量を見える化し、信頼される企業へ
CO2排出量を正確に算定・可視化することで、効果的な削減施策の立案が可能になり、取引先や投資家からの信頼性向上にもつながります。脱炭素経営を推進するうえで、CO2排出量の適切な管理と報告は欠かせない要素といえるでしょう。
以下の資料ではScope1~3の算定方法について、より詳しく解説しています。こちらもぜひご参考ください。


弊社のe-dashは「脱炭素を加速する」をミッションに、クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ 、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援をしています。
脱炭素に関するお悩み・課題はぜひ「e-dash」にご相談ください。


とは?-1-640x360.png)


とは?-640x360.png)
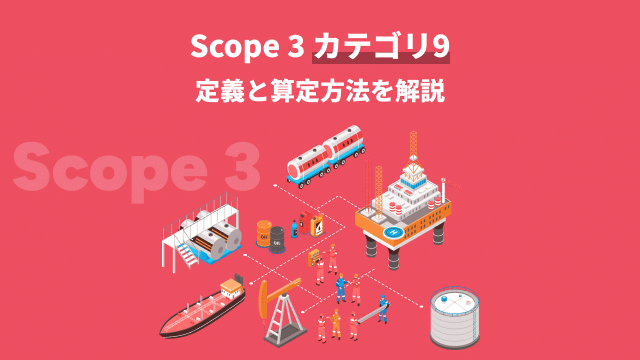

とは?-320x180.png)








