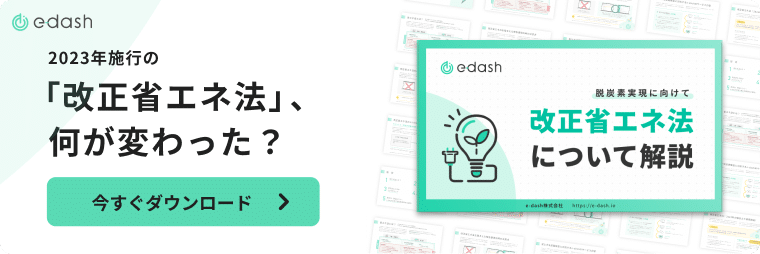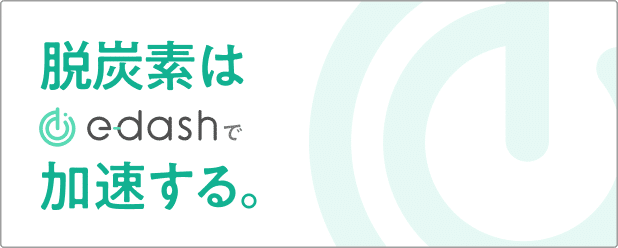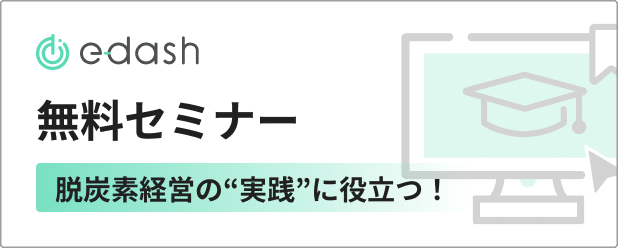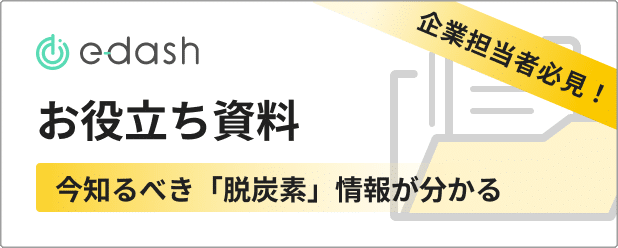SDGsの目標2「飢餓をゼロに」について、身近な問題に感じられない方もいるかもしれません。しかし、世界的に物流が発展し食糧が豊かになった現在でも、発展途上国をはじめさまざまな国で飢餓は深刻な問題です。そのため、世界中で飢餓を解消するための取り組みが行われています。また、日本にも飢餓の問題があることはご存知でしょうか。
この記事では、SDGs目標2の「飢餓をゼロに」の内容、世界や日本の飢餓の現状を解説します。また、日本企業がSDGsの目標2について取り組んでいる事例も取り上げます。
目次
SDGs目標2「飢餓をゼロに」とは?

SDGsの目標2「飢餓をゼロに」では、目指すゴールが以下のように定められています。
飢えをなくし、だれもが栄養のある食料を十分に手に入れられるよう、地球の環境を守り続けながら農業を進めよう
引用元:農林水産省「17の目標と食品産業とのつながり:目標2に対する取組」
ただ食べ物を得られたら良いのではなく、「環境を守りながら持続可能な農業を目指す」点が、SDGsならではの目標設定の仕方と言えます。
では、そもそも飢餓とはどのような状態のことでしょうか。
飢餓とは、身長に対して妥当とされる最低限の体重を維持し、軽度の活動を行うのに必要なエネルギー(カロリー数)を摂取できていない状態
引用元:WFP国連世界食糧計画「世界の飢餓状況
世界には、飢餓により命が危険な状態にある方が多くいます。世界中の人々が、栄養のある食糧を手に入れられる状況が継続するように、さらに詳細なターゲットが定められています。
SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは?
SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは、「持続可能な開発目標」の略称で、すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くための国際目標です。私たちが直面するグローバルな諸課題、例えば貧困、不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正などの解決を目指しています。
SDGsは、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っており、発展途上国だけでなく先進国自身も取り組むべきユニバーサル(普遍的)なものです。日本も積極的に取り組んでいます²。これらの目標は相互に関連しており、2030年までに各目標・ターゲットを達成することが重要です。
SDGs 17の国際目標SDGsの目標2「飢餓をゼロに」を達成するために、家庭でできる取り組みもあります。 食べきれる量を考えて買い物や料理をする:食品の無駄を減らすために、必要な量だけを購入します。大量に料理を作りすぎると、食べきれずに廃棄することになる可能性があります。そのため、食べきれる量だけを調理することが重要です。 賞味期限・消費期限をこまめにチェックする:食品の賞味期限や消費期限を確認し、期限が近いものから優先的に使用します。これにより、食品の廃棄を防ぐことができます。 食材を使い切る:一度に大量の食材を使わず、残った食材を次の料理に活用します。これも食品廃棄の防止につながります。 これらの取り組みは、家庭だけでなく、レストランや学校などでも実践できます。一人一人が少しずつ行動することで、大きな変化を生み出すことができます。SDGsの目標達成に向けて、私たち一人一人ができることから始めてみましょう。 >
- 貧困をなくそう
- 飢餓をゼロに
- すべての人に健康と福祉を
- 質の高い教育をみんなに
- ジェンダー平等を実現しよう
- 安全な水とトイレを世界中に
- エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
- 働きがいも経済成長も
- 産業と技術革新の基盤を作ろう
- 人や国の不平等をなくそう
- 住み続けられるまちづくりを
- つくる責任、つかう責任
- 気候変動に具体的な対策を
- 海の豊かさを守ろう
- 陸の豊かさも守ろう
- 平和と公正をすべての人に
- パートナーシップで目標を達成しよう
SDGs目標2「飢餓をゼロに」のターゲット
「飢餓をゼロに」を達成するために、次のような目標が設定されています。
| ターゲット | |
| 2.1 | 2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 |
| 2.2 | 5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 |
| 2.3 | 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 |
| 2.4 | 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 |
| 2.5 | 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 |
| 2.a | 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 |
| 2.b | ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 |
| 2.c | 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 |
(※2.1〜2.5はターゲット、2.a〜2.cがそれを実現するための手段です。)
簡単にまとめると、以下の内容を示しています。
・貧困層の人々がいつでも栄養のある食事を摂れるようにする
・子どもや妊産婦、高齢者など、特に栄養を必要としている人々の栄養不良をなくす
・小規模生産者の生産性や収入増加および雇用創出、適正な収入獲得を実現させる
・災害に強い農業技術の開発と伝達・習得を目指す
【世界】飢餓の現状と問題点・課題とは

2021年時点で、世界では8億2,800万人が十分な食事を摂ることができず、飢餓状態に晒されています。これは、世界の総人口から見ると約10人に1人の割合です。さらに、そのうち4,500万人は命の危機が迫る緊急的な状況にあるとされています。
世界の飢餓の現状
世界ではフードロスが大きな問題となっている一方で、およそ5.6秒に1人の割合で飢餓によって命を失い、飢餓のために5歳まで生きられない子どもが年間に560万人もいるのが現状です。
SDGs2を進めるべき世界の飢餓の問題点
もっとも飢餓人数が多い地域がアジアです。5億人以上の人々が飢餓で苦しんでおり、その多くが南アジアに集中しています。
世界的に、飢餓の原因は干ばつや洪水、戦争・紛争によるものが多いですが、先進国の食品ロスも原因の一つです。一説によれば、食品として生産されたもののうち、約3分の1にあたる約13億トンもの食糧が何らかの形で廃棄されていると言われています。さらに、近年世界中に影響を与えた新型コロナウィルス感染症も深刻化させた原因の一つとされており、飢餓は世界各国が取り組むべき重要な問題なのです。
SDGs目標2「飢餓をゼロに」への世界での取り組み事例

SDGsの目標2「飢餓をゼロに」に関する各国の取り組み事例をご紹介します。これらの事例は、世界各国で行われているフードロス対策と、国連世界食糧計画(WFP)の活動について詳しく説明しています。それぞれの取り組みがどのように飢餓問題の解決に寄与しているかご覧ください。
各国でのフードロス対策
フランス
フランスでは2016年に食品廃棄禁止法が施行されました。この法律では、売り場面積が400平方メートル以上のスーパーマーケットに対して、売れ残った食品を慈善団体等へ寄付することが義務付けられています。食品を廃棄した場合、罰金が科されます。
イタリア
フランスと同年に食品廃棄禁止法が成立しました。この法律では、食品を意図的に廃棄することが禁じられており、売場面積400平方メートル以上のスーパーマーケットは慈善団体との食品寄付の契約を締結するよう義務付けられています。
国連WFPの活動
国連世界食糧計画(WFP)は、飢餓のない世界を目指して活動する国連の人道支援機関です。紛争や自然災害などの緊急時に食料支援を届けるとともに、途上国の地域社会と協力して栄養状態の改善と強い社会づくりに取り組んでいます。また、120以上の国と地域に拠点を持ち、飢餓から命を救う緊急支援から未来を変える開発支援まで幅広い活動を展開しています。
-ja.wfp_.org_-1024x198.png)
【日本】飢餓の現状と問題点・課題とは

日本においては、飢餓状態にある方を身近に感じる機会は少ないかもしれません。しかし、日本でも飢餓状態にある方は多く、それに気付きにくい状況であることが社会問題となっています。
日本の飢餓の現状
日本は食糧調達面でも問題を抱えているため、飢餓は決して他人事ではないのです。
生きるうえで必要最低限の生活水準が満たされていない「絶対的貧困」に対し、日本で問題となっているのは、「相対的貧困」に悩む人々の現状です。
相対的貧困とは、今日食べる食事に困る状況にあることを指します。着ている衣服や家の様子などからは可視化されない相対的貧困は、日本でも深刻な社会問題の一つです。
相対的貧困に陥っているために十分な食事と栄養を摂れない子どもたちがいます。日本の相対的貧困率は15.7%、ひとり親家庭に限れば50%以上にも及ぶため、日本にも飢餓問題があることを認識しなければなりません。
SDGs2を進めるべき日本での飢餓の問題点
ほかにも日本の課題として挙げられるのが、農業人口の減少と食料自給率の低さです。農業従事者の高齢化に伴い、必然的に農業人口が減少しています。
食生活の変化によって日本の食糧自給率も減少傾向にあるため、いざというときに食糧難に陥るリスクについても考えなければなりません。農業人口や食糧自給率の問題は、日本の飢餓につながるため、真剣に取り組むべき課題です。
SDGs目標2「飢餓をゼロに」に対する企業の取り組み事例

SDGsの目標2「飢餓をゼロに」に対し、日本ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。ここでは、以下の企業が取り組んでいる事例をご紹介します。
- 味の素株式会社
- 株式会社伊藤園
- 敷島製パン株式会社(Pasco)
- キユーピー株式会社
味の素株式会社
味の素株式会社では、フードロスを減らすために以下の点に力を入れて取り組んでいます。
- 生産工程のロス削減
- 廃棄削減に役立つ製品開発
- 需給バランスの見極め、賞味期限延長
- 生活者へのロス削減普及活動
また、味の素はアミノ酸についての知見を活用し「食と健康の課題解決への貢献」を目指しています。「10億人の健康寿命の延伸」「環境負荷の50%削減」の2つが、具体的な取り組み目標です。
味の素グループの食品は、世界130ヵ国以上に届けられており、その利用者は7億人に及びます。味の素ならではのネットワークを活かして、おいしくて栄養のある食べ物に世界中の誰もがアクセスできるよう、さまざまな活動が行われているのです。
株式会社伊藤園
株式会社伊藤園の取り組みは「持続可能な国内農業への貢献」です。その一環として、荒廃農地を活用して茶畑に契約栽培を行うことで、茶農家の安定経営や原材料の安定した供給を目指します。
また、生産者と協働しながら高品質の原料を作り強固な関係性を築くことで、高品質原料の安定調達と持続可能な国内農業の発展に貢献することも取り組みの一つです。
さらに、地元の事業者をサポートしながら利用されていない土地を大規模な茶園にし、生産された茶葉を伊藤園商品用に買い取りも実施。世界に通用する独自の農業モデルの進化を図り、九州や静岡、埼玉など日本の各地で新産地事業を展開しています。
敷島製パン株式会社(Pasco)
食パンのブランド「超熟」で知られるPascoでは、国産小麦を活かしたパンづくりを通じて、食料自給率の向上に貢献することを目指します。
現在、日本の小麦食糧自給率は約15%、なかでもパン用小麦はさらに低くほとんどが輸入品です。そのため、Pascoは小麦の生産者や国や行政、共同研究している大学などさまざまな専門家と協力し、Pasco製品における国産小麦の使用率を2030年までに20%まで引き上げることを目標としています。
また、貧困に苦しむ⼦どもたちや学⽣の支援も取り組みの一つです。Pascoの余剰製品をこども食堂やフードバンク、セーブ・ザ・チルドレンなどに提供しており、食事に困っている子どもたちの支援に加えて、フードロス対策としても有効な活動と言えます。
キユーピー株式会社
キユーピー株式会社は、2007年よりフードバンク活動をする団体である認定NPO法人の支援を始めました。現在では、日本全国で15のフードバンクやMOWLS(こども食堂をはじめ、子どもや高齢者などの「居場所」に集う人が食事ができるシステム)に食糧品を寄贈しています。
また、2017年には一般財団法人キユーピーみらいたまご財団を設立。独自の食育や、長期的な視点で、持続可能な社会の実現に貢献する活動を継続中です。
さらに、国連世界食糧計画が主体となって行う「WFPレッドカップキャンペーン」にも参加しています。レッドカップキャンペーンのロゴマークが付いた商品を消費者が買うと、売上金の一部が企業から寄付され、WFPから世界の子どもたちへの学校給食になる仕組みです。
SDGs目標2「飢餓をゼロに」について企業ができるアプローチ
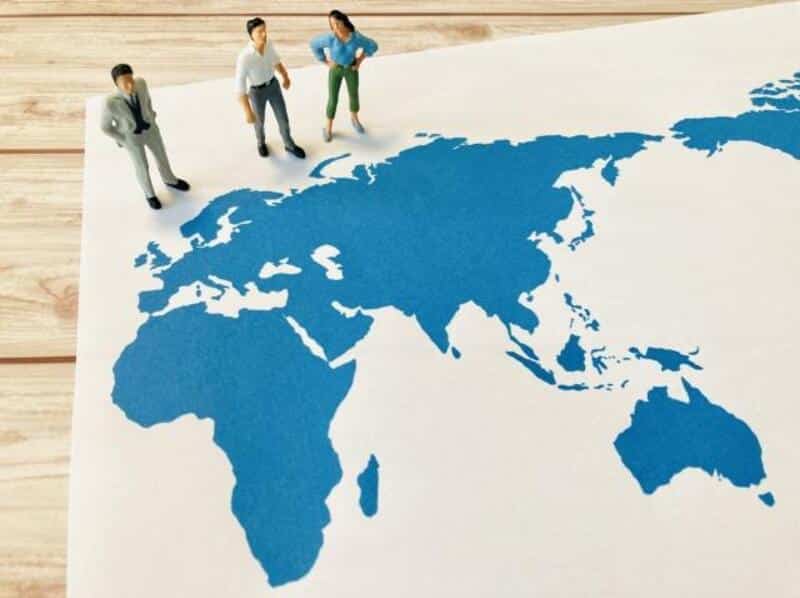
「飢餓をゼロに」を実現するために、日本の企業ができるアプローチとはどのようなものなのでしょうか。実際に行われていることも含めて紹介します。
生産技術支援・農業従事者の所得確保支援
日本の農業技術は世界のなかでも優れていることから、ノウハウを途上国の生産者に伝えることで、途上国の生産性の向上が期待できます。また、農作物の収穫・保管から販売にいたるまでのシステムを整備することで生産者の所得確保にも貢献できるでしょう。
栄養不良の改善
飢餓状態にある人々が食糧を手にできるよう、栄養価の高い食糧の物資支援をしています。また、栄養や健康に関する知識を共有することも有効な手段です。
食品ロス削減、食糧支援
直接的な支援でなくても、飢餓問題に対してできることがあります。食べ物を買いすぎない、まだ食べられるものを捨てない、フードバンクの活用などで食品ロスを削減することは、消費者レベルでもできることです。
また、マッチングアプリやフードシェアリングサービスなどで、飢餓や貧困状態にある方の支援をする事業も行われています。
代替食の開発
環境負荷が大きいと言われる畜産食肉の代替として、環境への影響が少ないタンパク質源が開発・製造されています。よく耳にするものとして大豆ミートが代表的ですが、ほかにも昆虫食や培養肉も注目されています。
SDGs目標2の推進で私たちにできること

SDGsの目標2「飢餓をゼロに」を達成するために、家庭でできる取り組みもあります。
- 食べきれる量を考えて買い物や料理をする:食品の無駄を減らすために、必要な量だけを購入します。大量に料理を作りすぎると、食べきれずに廃棄することになる可能性があります。そのため、食べきれる量だけを調理することが重要です。
- 賞味期限・消費期限をこまめにチェックする:食品の賞味期限や消費期限を確認し、期限が近いものから優先的に使用します。これにより、食品の廃棄を防ぐことができます。
- 食材を使い切る:一度に大量の食材を使わず、残った食材を次の料理に活用します。これも食品廃棄の防止につながります。
これらの取り組みは、家庭だけでなく、レストランや学校などでも実践できます。一人一人が少しずつ行動することで、大きな変化を生み出すことができます。SDGsの目標達成に向けて、私たち一人一人ができることから始めてみましょう。
SDGs目標2「飢餓をゼロに」の取り組み事例を参考に、自社でできることを考えよう

「飢餓は遠い国の問題」と感じている方もいるかもしれません。しかし、世界では8億人以上の人が十分な食事を摂ることができず、日本国内でも貧困による栄養不良・飢餓に悩む方がたくさんいます。また、農業人口の減少や食料自給率の低さも、日本では飢餓につながる大きな課題です。
SDGsの目標2「飢餓をゼロに」は、日本で暮らす私たちにとっても身近な問題であることを認識しなければなりません。国内の食品メーカーが行っている取り組み事例や企業・個人ができるアプローチ方法を参考に、自社でできる取り組みについて検討してみてはいかがでしょうか。