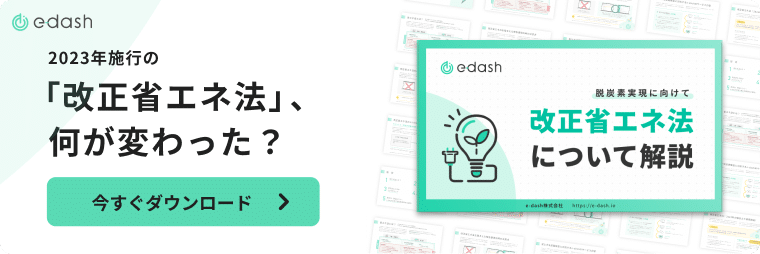世界中で大きな問題を抱えている気候変動。地球温暖化、海面上昇、干ばつ、異常気象の頻発などさまざまな問題をもたらしています。
このような状況を受け、SDGsの13番目の目標では「気候変動に具体的な対策を」が定められました。
本記事では、SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」の意味や現状、政府や企業による具体的な取り組みについて解説します。
目次
SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」の意味やターゲット

SDGsとは、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称で、「誰一人取り残さない」社会を実現するために、2030年までに17の国際的な目標を定めたものです。
17の目標の下には169のターゲットが決められており、環境や教育、貧困など多くの課題に世界全体で取り組んでいます。
なかでも、13個目の目標である「気候変動に具体的な対策を」は、世界の至る所で発生する異常気象の原因とされる気候変動を解決するための対策を決めることがポイントです。
今後、気候変動を緩やかにするための「緩和」と、すでに起きている異常気象等の自然災害を軽減するための「適応」の2つに分け、具体的な対策が話し合われています。
SDGsとは
SDGsは、Sustainable Development Goals(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ)の略称で、一般的に「エス・ディー・ジーズ」と呼ばれます。意味は、持続可能な開発目標というもので、2015年9月に開催された国連サミットにて採択されました。具体的な国際目標として、2030年を期限とした17の国際目標と169のターゲット・231の指標が定められています。
SDGs 17の国際目標
- 貧困をなくそう
- 飢餓をゼロに
- すべての人に健康と福祉を
- 質の高い教育をみんなに
- ジェンダー平等を実現しよう
- 安全な水とトイレを世界中に
- エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
- 働きがいも経済成長も
- 産業と技術革新の基盤を作ろう
- 人や国の不平等をなくそう
- 住み続けられるまちづくりを
- つくる責任、つかう責任
- 気候変動に具体的な対策を
- 海の豊かさを守ろう
- 陸の豊かさも守ろう
- 平和と公正をすべての人に
- パートナーシップで目標を達成しよう
SDGs目標13のターゲット
SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」に設定されているターゲットは、5つあります。
まず、以下の3つに記されているのは「気候変動に具体的な対策を」の達成目標です。
13.1:すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応力を強化する。
引用元:国連総会|我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
13.2:気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。
13.3:気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。
続いて、以下の2つには、目標を達成するための具体的な方法が記されています。
13.a:重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020 年までにあらゆる供給源から年間 1,000 億ドルを共同で動員するという、UNFCCC の先進締約国によるコミットメントを実施し、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。
13.b:後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する
引用元:国連総会|我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」が求められる理由

SDGs目標13が求められているのは、世界で起きているさまざまな異常気象などの変化が気候変動によりもたらされているからです。
例えば、海水の温度上昇によるサンゴの消滅が危惧されており、海水が1.5℃上昇することで70〜90%消滅、2℃上昇することで完全に消滅するとされています。
また、温暖化による海面上昇が問題になっていますが、2100年までに30〜60cmほど上昇してしまうことが想定されており、ツバルのような1mほどしか高さがない国は水没してしまうかもしれません。
さらに、世界中で干ばつが起きており、2030年までに推定7億人が故郷を離れざるを得なくなる想定もあります。
加えて、日本でも近年頻繁に見られるようになった台風やゲリラ豪雨による災害のような、中・大規模災害が2015年から2030年で40%増加するという想定もされているほどです。
このような異常気象を止めるためには、気候変動対策をおこなう必要があります。
SDGs目標13 達成の現状と、今後の気候変動

しかし、SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」はあまり達成されていない現状があります。二酸化炭素(CO2)は地球温暖化の主な原因だと考えられていますが、エネルギー関連の二酸化炭素(CO2)排出量は2021年に過去最高水準に達してしまいました。
また、気候変動対策資金として先進国は年間1,000億ドルを提供するという公約も達成されず、2019年には年間796億ドルにとどまっています。
取り組みが足踏み状態を続けているため、気候が好転することはなく、世界の気温上昇は続き、今でも各地で異常気象が起き続けているのです。
日本の気候変動の現状
気候変動は、各地で既に大きな被害をもたらしています。下記の記事でそれぞれの詳しく説明していますが、主な影響としては以下の通りです。
- 自然災害の増加:2017年の九州北部豪雨災害など
- 猛暑日の増加:熱中症による死亡者数が大幅に増加
- 動植物の減少・食糧不足:穀物や野菜、果実などが育ちにくくなり収穫量が減少
- 砂漠化:豪雨による土壌の流出で、環境が整えられない
早ければ2030年までに気温が「1.5度上昇する」といわれる
国連は2021年の「第6次評価報告書」で、地球温暖化の影響により、2030年頃までに1.5度、地球の平均気温が上昇することを公表しました。この気温上昇は、主に人間活動による二酸化炭素などの温室効果ガスの排出が原因とされています。
気温が上昇すると、極端な天候、海面上昇、生態系の変化などさまざまな影響が生じ、人々の生活に直接的に影響を与える可能性があります。
問題の解決には、私たち一人ひとりが地球温暖化防止に取り組むことが重要です。エネルギー効率の良い製品を選ぶ、再生可能エネルギーを利用する、公共交通機関を利用するなど、日常生活の中で地球温暖化防止に貢献できる行動はたくさんあります。
SDGs目標13や気候変動に対する日本の取り組みの現状

気候変動に対して、日本でもさまざまな取り組みがおこなわれています。パリ協定ではすべての国が5年ごとに温室効果ガスの排出削減目標を提出する義務があります。
日本も2015年の段階で、温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比-26%とする目標を掲げました。
5年後の2020年にも同様の水準である2030年度に2013年度比-26%とする目標を掲げつつ、この水準にとどまるわけではなく、さらなる削減も追及することを決定しました。
2050年へ向けた「カーボンニュートラル宣言」
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均等させることです。2021年に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、2050年のカーボンニュートラルに向けて、2013年度から46%削減することを新たな目標として掲げ直しました。
さらに、46%にとどまることなく50%を達成できるように、より一層強力な対策をおこなうことも同時に目標として掲げています。
SDGsに対する学生の意識も高まっている
SDGs17の目標は、テレビや雑誌で大きく取り上げられるようになり、高校教育で取り入れられる機会も年々増加しています。
しかし、SDGsは「世界のどこかで議論されている、すぐに自分には関係しないこと」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。最近では、SDGsを学習カリキュラムに盛り込むための教職員向けセミナーが実施されており、小学生のうちから環境保護を意識できるような流れができています。
こちらの記事では、高校生によるSDGsの取組事例を紹介しています。
SDGs目標13や気候変動に対する企業の取り組み事例

日本政府だけでなく、企業も気候変動に対する取り組みをおこなっています。今回は、そのなかでも以下の3社の事例を取り上げます。
- リコー
- ANA
- マクドナルド
それぞれの会社の取り組みを見てみましょう。
リコーの取り組み
株式会社リコーでは、気候変動対策として、脱炭素化に力を入れ、2030年度には2015年比で温室効果ガスを63%削減する目標を立てています。
また、再生可能エネルギーの利用促進にも取り組んでおり、2017年から、再生可能エネルギー100%化にコミットする企業の国際イニシアティブである「RE100」に日本企業で初めて加盟してから、積極的な活動をおこなっているのです。
目標としては、2030年には使用電力の50%を、2050年には100%を再生可能エネルギーで賄うことを掲げています。
ANAの取り組み
ANAでは、2050年までに航空機の運航で発生するCO2排出量を実質ゼロにすることを目標として掲げています。
そのために、CO2の排出量を削減できる燃料(SAF)の活用や技術革新、オペレーション上の改善、排出権取引制度の活用という4つを柱として掲げて、取り組みをおこなっています。
なかでも、SAFの活用はCO2の排出量削減には必要不可欠であるため、日本航空株式会社とも協力しながら国産SAFの普及・拡大に向けた取り組みが進められているのです。
マクドナルドの取り組み
マクドナルドでは、2050年までに、店舗・オフィス・サプライチェーンの全体でネット・ゼロ・エミッションを達成することを目標としています。
ネット・ゼロ・エミッションとは、人間が排出する温室効果ガスの量と人間が大気中から除去する温室効果ガスの量がプラスマイナスゼロの状態のことです。
その第一歩として、2022年から、再生可能エネルギーに由来した電力を一部の店舗にて導入を開始しています。
そのほかにも、さまざまな省エネ施策を通じてエネルギーの効率化を進め、気候変動への対策を講じていくとされています。
その他、海外企業の取り組み事例や、私たち一人ひとりができる行動についてを、別の記事で詳しく紹介しています。
SDGsへの取り組みは企業や自治体にも求められる

世界で大きな注目を集めているSDGsでは、政府が主導してさまざまな取り組みがおこなわれています。
なかでも、気候変動に対してはパリ協定に対する目標設定や「地球温暖化対策計画」など、前向きな取り組みがいくつもなされています。
しかし、政府だけでは目標が達成できるわけではありません。リコーやANA、マクドナルドなどの企業、さらには自治体も積極的に気候変動への取り組みを行うことで、より早期に問題が解決に向かうことが考えられます。
SDGsへの取り組みに関心があるが、何から始めて良いかお困りの企業・自治体はe-dashへご相談ください。
e-dashは、現状を把握するCO2排出量の可視化からエネルギー最適化の提案、CO2削減までを総合的にサポートするサービスプラットフォームです。SDGsへの取り組みに寄り添うパートナーをお探しなら、ぜひe-dashにご相談ください。