
欧州連合(EU)は、EU域内に流通する電池(バッテリー)に関わる環境負荷を低減する包括的なルールとして、欧州電池規則を2023年に施行しました。本記事では、欧州電池規則と対象となる電池や事業者、日本企業への影響までわかりやすく解説します。
目次
欧州電池規則とは?

欧州電池規則(European Battery Regulation)とは、EU域内で流通・使用されるあらゆる種類の電池(バッテリー)を対象に、その生産・販売・流通・使用・回収・リサイクルといったライフサイクル全体を包括的に管理するための規制です。
この規則は、2006年に施行された「電池指令」を改正・強化したものであり、2020年12月に欧州委員会が規制案を公表、その後の議会および理事会での審議と三者協議を経て、2023年8月に正式に発効されました。
本規則の目的は、電池に起因する環境負荷を最小限に抑えることにあります。そのため、EU域内で電池を製造・流通させるすべての事業者に対し、規模や所在に関係なく規制が適用されます。これは、EUに電池単体や、電池を組み込んだ製品(自動車、電子機器など)を輸出する日本企業にとっても遵守必須の法規制です。対応を怠った場合、EU市場へのアクセスが事実上不可能になるため、早期の対策が求められます。
規則は全14章96条および15の附属書から構成されており、主に以下の5つの領域において事業者に遵守を求めています。
| ・電池の持続可能性(カーボンフットプリント(CFP)、リサイクル含有率など) ・電池の安全性と性能 ・情報の透明性とデジタルバッテリーパスポートの導入 ・回収・リサイクル義務の強化 ・デューデリジェンス(DD)義務(サプライチェーン上の人権・環境リスク管理) |
このように、電池のライフサイクル全体を通じた環境配慮を義務化することで、循環型社会の実現やカーボンニュートラル達成に貢献することが期待されています。
欧州電池規則の目的
欧州電池規則の主要な目的は、EU域内で使用される電池の持続可能性、循環性、安全性を高めることにあります。バッテリーのライフサイクル全体を持続可能なものとすることを目指し、原材料の調達から使用済みバッテリーの回収・リサイクルまでを包括的に管理します。
また、輸入化石燃料から自立しクリーンエネルギーへ転換し、競争力の高いバッテリー産業を確立することも重要な目標となっています。
欧州電池規則が制定された背景
EUは2019年に「欧州グリーン・ディール」を発表し、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを掲げました。この戦略には持続可能なEU経済の実現に向けた法案が盛り込まれており、以下の計画などが含まれています。
| ・航空燃料への課税(※) ・2035年以降のガソリンおよびディーゼル車の販売禁止 |
これらの政策は、必然的にEV(電気自動車)や蓄電池の需要を急増させます。その結果、電池の原料となるリチウムやコバルトといった特定資源の確保が地政学的なリスクとなる一方、製造・廃棄段階での環境負荷増大も懸念されるようになりました。こうした背景から、経済安全保障と環境保護を両立させる戦略的枠組みとして、欧州電池規則が制定されたのです。
(※)EUの航空燃料への課税
EUが進める、航空燃料への新たな税制度。地球温暖化対策として、CO2排出量の削減を主な目的とし、「欧州グリーン・ディール」政策の一環として提案されました。具体的な導入時期や詳細は、現在も加盟国間で調整段階にあります。
欧州電池規則の対象となる電池

欧州電池規則において対象となる電池は以下の通りです。軍事、宇宙、原子力目的を除き、EU域内で販売されるすべての電池製品に適用されます。
| 電動車載用電池 | ・電気自動車に搭載されている電池(ハイブリッド車搭載の電池含む) ・欧州電池規則では搭載している自動車のカテゴリや電池の重量により対象を限定 |
| LMT電池 (軽輸送手段用電池) | ・電動モータのみ、もしくは電動モータと人力の併用を駆動力とする車輪付き車両の牽引用の電力を供給するために設計された電池 ・電動スクーター、電動自転車、小型電動車両など ・欧州電池規則では密閉され、重量が25 kg以下のもの |
| 産業用電池 | ・事業活動、農業、各種産業機械、または鉄道、船舶、航空機など電気自動車以外の輸送手段の動力源として設計された電池 ・エネルギー貯蔵システム(ESS)に用いられる蓄電池 ・他のカテゴリに該当しない全ての電池も産業用電池と見なされる場合がある |
| SLI電池 (始動・照明・点火用電池) | ・自動車のエンジン始動、照明、点火のために電力を供給する電池 ・車両の補助的機能や快適機能のための電力も供給するもの ・化学組成の電池(12V鉛蓄電池など) |
| ポータブル電池 | ・密封型で、重量が5kg以下の電池 ・一般消費者が容易に持ち運び可能な機器に使用されるもの ・産業用、自動車用、LMT用ではないもの ・スマートフォン、ノートパソコン、電動工具、玩具などに使用される充電式・非充電式の電池 ・ボタン電池 |
欧州電池規則の対象となる事業者
欧州電池規則の対象となるのは、電池のライフサイクル全体に関与するさまざまな事業者です。
そのうち、電池をEU市場に供給または流通させる事業者は、「経済事業者」という包括的な概念で定義されています。たとえば、第三国から電池を輸入する企業や、電池を組み込んだ製品をEU内に供給する企業も含まれます。
また、経済事業者に限らず、リサイクルプロセスに関与するリサイクル業者や廃棄物管理事業者なども規則の適用対象です。つまり、EU域内における電池の設計、製造、輸入、販売、使用、そして廃棄・リサイクルに至るまでのサプライチェーン全体に関わる広範な事業者が、この規則の対象となります。
| 【対象となる事業者の例】 ・経済事業者:製造者、流通業者、輸入者、生産者(生産者責任組織)、認定代理人 など ・リサイクル関連事業者:リサイクル業者、廃棄物管理事業者 など ・その他関係者:エンドユーザー など |
欧州電池規則の主な5つの規定事項
欧州電池規則は主に5つの規定から構成されており、それぞれ順次実施される予定です。
それぞれの規定について確認していきましょう。
カーボンフットプリント(CFP)対応
カーボンフットプリント(CFP:以下CFP)とは、製品のライフサイクル全体を通したGHG排出量をCO2排出量に換算した値です。ライフサイクルとは原材料調達からリサイクル・廃棄までを指します。欧州電池規則は電池のCFP値の算定、表示・開示を事業者に課しており、規制の主な対象者は電池の製造事業者です。対象電池は電動車載用電池、LMT、産業用電池(2kWh以上)です。
適用開始は、関連する委任法の発効から12カ月後とされています。また、電池の種類ごとに対象となる規制が異なり、製造事業者や販売者など、関与する主体も異なります。
CFP対応は2025年後半の規制開始が予定されていましたが、細則の未公表により、施行が延期される見通しとなっています。
| 【電池種類ごとのCFP表示義務の適用・対象規制・対象者の違い】 | |||
|---|---|---|---|
| 電池の種類 | CFP表示義務の適用 | 対象規制 | 主な対象者 |
| 電動車載用電池 | あり | CFP、再生材含有率、回収義務など | 製造事業者 |
| LMT | あり | CFP、回収義務 | 製造事業者、一部販売者 |
| 産業用電池(2kWh以上) | あり | CFP、再生材含有率、耐久性など | 製造事業者 |
| ポータブル電池 | なし(CFP対象外) | 回収目標、含有物制限など | 一般消費者向け販売業者 |
| SLI(自動車始動用等) | 現時点ではなし | 再生材含有率(鉛)など | 製造事業者 |
デューデリジェンス(DD)対応
欧州電池規則では、人権と環境に関するデューデリジェンス(DD)が重要な要素として位置づけられています。このことから、原材料調達をはじめ、サプライチェーン全体で人権侵害や環境リスクを特定・評価し、これらを防止・軽減する義務があります。
対象者は前会計年度の純売上高が4,000万ユーロ以上の経済事業者で、コバルト、リチウム、ニッケル、天然黒鉛などの重要原材料を扱う事業者が含まれます。2025年8月18日から適用開始予定でしたが、2027年8月18日からの適用に延期されました。この延期は、原材料の調達リスクや認証制度の遅れを受け、企業や関係機関がサプライチェーンの見直しや、体制構築に必要な準備期間を確保するための措置とされています。
バッテリーパスポート(BP)の導入
バッテリーパスポート(BP:以下BP)とは、蓄電池に付与する電池のライフサイクルに関する電子記録です。ブロックチェーン技術や二次元コードを使用し、サプライチェーン全体で開示・記録ができます。
欧州電池規則は電池情報の統一性・透明性・流通性のためBPの付与を義務付けており、電池の基礎情報や固有情報等の正確な提示・更新・保管義務が課されます。対象者は市販、使用する経済事業者、リユース・リパーパス・再製造された電池を市販/使用する経済事業者です。対象電池は電動車載用電池、LMT、産業用電池(2kWh以上)で2027年2月18日義務化実施の予定です。
最低再生材含有率の義務化
欧州電池規則では、段階的な義務が設定されています。
1. 2028年8月18日から製造事業者は、コバルト、鉛、リチウム、ニッケルのリサイクル材含有率を開示する義務を負います。
2. 2031年8月18日から上記の開示義務に加え、定められた最低含有率の達成が義務化されます。
対象となる電池は以下の電池で、製造事業者は欧州委員会が定める方法に従い、含有率を算定・報告しなければなりません。
| ・電動車載用電池 ・LMT電池 ・産業用電池 ・SLI電池 |
2031年からの最低含有率はコバルト16%、鉛85%、リチウム6%、ニッケル6%とされ、2036年にはさらに高い基準(コバルト26%、リチウム12%、ニッケル15%、鉛は据え置き)が予定されています。
【回収目標の設定】使用済み電池の回収・リサイクル義務
欧州電池規則では材料回収率・リサイクル効率の算定と、最低目標値を設定しています。対象者は電池のリサイクラーで、目標値を上回る材料回収率・リサイクル効率を達成しなければなりません。
対象電池は全ての電池です。さらに廃棄電池の回収を生産者、生産者が選任する生産者責任組織に課しており、回収率の目標達成、回収拠点の設置を義務付けています。
ポータブル電池は2030年末までに73%、LMT用電池は2031年末までに61%の回収率達成が求められ、義務化実施日は対象電池や義務内容により異なります。
欧州電池規則が日本企業にもたらす影響

出典:IPA「サプライチェーン上のデータ連携の仕組みに関するガイドラインα版(蓄電池CFP・DD関係)」をもとに作成
欧州電池規則は、EU域内の電池サプライチェーン全体にわたる事業者を対象としていますが、サプライチェーンが国際的に広がる現代において、日本の事業者も決して無関係ではいられません。規則への対応を怠った場合、日本企業も以下のような、「3つの危機」に直面する可能性があります。
| 1.自社製品が売れない 2.規制に対応した部品や原材料が買えない 3.サプライチェーン情報が他社に把握される(覗かれる) |
しかし、CFP算定やデューデリジェンスの実施、サプライチェーン全体の可視化にはコストや体制構築の面で高いハードルが存在します。
その一方で、バッテリーパスポート関連技術の開発やコンサルティングなど、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。こうした中、経済産業省が主導する「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」では、CFP算定ルールの策定や人権・環境デューデリジェンスに関する試行事業などを進めており、日本企業に対して積極的な参加と対応準備を呼びかけています。
欧州電池規則をビジネス成長の機会とするために
欧州電池規則はCFP開示やデューデリジェンス、再生材利用、回収目標の設定など、多岐にわたる対応をサプライチェーン全体に求めており、EU域外の日本企業もその影響は避けられません。
この変化を単なる規制強化と捉えるだけでなく、早期に情報を収集し戦略的に取り組むことで、持続可能なビジネスモデルへの転換や新たな事業機会の創出にもつながります。複雑化する脱炭素経営においては、的確な情報収集と専門的なサポートの活用が成功の鍵となるでしょう。
弊社の「e-dash」では、「脱炭素を加速する」をミッションとして掲げています。クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援を行っています。
以下の資料では、CFPの基本について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
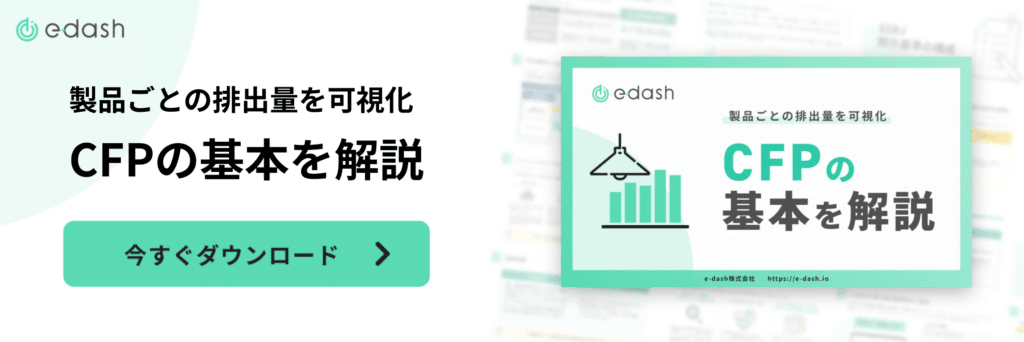


とは?-1-640x360.png)


とは?基礎知識から実践の注意点まで徹底解説-2-320x180.png)









