とは?-1-1024x576.png)
世界的に脱炭素社会への移行が加速するなかで、製品やサービスの環境価値を可視化する手段として、削減実績量(REP)に注目が集まっています。本記事では、削減実績量(REP)の概要から、他の削減量に関する指標との違い、メリットやデメリットまでをわかりやすく解説します。
目次
削減実績量(REP)とは?
のイメージ.png)
削減実績量(REP)とは「Reduced Emissions of Product」の略で、企業が自社の排出削減施策により実際に減らした温室効果ガス排出量を、製品単位で示すものです。企業のGX(グリーントランスフォーメーション:以下、GX)への取り組みを製品レベルで「見える化」する目的があり、この値が大きいほどGX価値の高い製品とみなされます。
カーボンクレジットのように、取引を通じて他者の排出削減には使用できませんが、自社努力の成果を可視化する手段として注目されています。ただし、まだ具体的な定義や算定・主張手法が確立されておらず、今後の整備が課題となっています。
削減実績量が注目される背景
脱炭素に向けた取り組みが企業にとって不可欠となるなかで、製品やサービスの環境価値を「見える化」して競争力に結びつける手段として、削減実績量が注目されています。とくにGXが求められる今、排出削減を単なるコストではなく、付加価値の創造による競争力の獲得・向上の手段とする視点が重要です。
削減実績量は、脱炭素投資によって生まれた環境価値を示すものです。そのため、外部へのアピール材料となり、ESG評価やサプライチェーン対応、エシカル消費などへの活用が期待されます。
また、排出量の取引にとどまらず、製品自体の削減価値を訴求する手段としても役割は拡大してきており、今後、他の制度や政策との連携も注目されています。
GXへの取り組みの重要性

世界全体で脱炭素に向けた取り組みが進展しているなかで、企業の気候変動対策においても、自社だけでなく社会全体の排出削減への貢献が評価されています。このような背景から、GXへの取り組みの重要性が高まってきました。
GXとは、温室効果ガスの排出削減を目指し、その活動を経済成長にもつなげていこうとする、経済社会システム全体の構造転換を図る取り組みのことです。とくに、削減実績量などによってGX価値を示すことは、顧客や投資家などからの信頼獲得と、持続的な企業価値の向上につながります。
削減実績量と他指標の違い
| 削減実績量(REP) | カーボンフットプリント(CFP) | 削減貢献量(AEP) | |
| 算定対象 | 製品 | 製品 | ソリューション |
| 表す量 | 削減量 | 排出量 | 削減量 |
| 国外ルール | なし | ・ISO14067 ・GHGプロトコル | WBCSDガイダンス等 |
| 国内ルール | なし | CFPガイドライン | 削減貢献量算定ガイドライン |
削減実績量と、他の削減量に関する指標の違いはどのような点にあるのでしょうか。それぞれの特徴について解説します。
カーボンフットプリント(CFP)
カーボンフットプリント(CFP)は、製品やサービスのライフサイクル全体を通じて排出される温室効果ガスの量を、CO2に換算して表示する仕組みです。製品の排出量を数値化することで、環境負荷の把握や他製品との比較に用いられます。
ただし、製品の排出量を「絶対値」で示すため、カーボンフットプリント(CFP)単体では、排出削減の効果を証明することはできません。
削減貢献量(AEP)
削減貢献量(AEP)は、自社の製品やサービスの普及を通じて、他社や社会全体の温室効果ガス排出削減にどれだけ貢献したかを定量化する指標です。Scope 4とも呼ばれます。製品の使用段階などでの排出削減効果を数値化することで、社会全体への貢献や顧客・消費者への寄与を「見える化」することが可能です。
ただし、一定の想定に基づく見積もりであるため、実際の削減量と異なる可能性があることに注意が必要です。削減貢献量(AEP)の主張にあたっては、前提条件や算定方法などの明確な開示が求められます。
削減実績量のScope 1・2・3との関係性
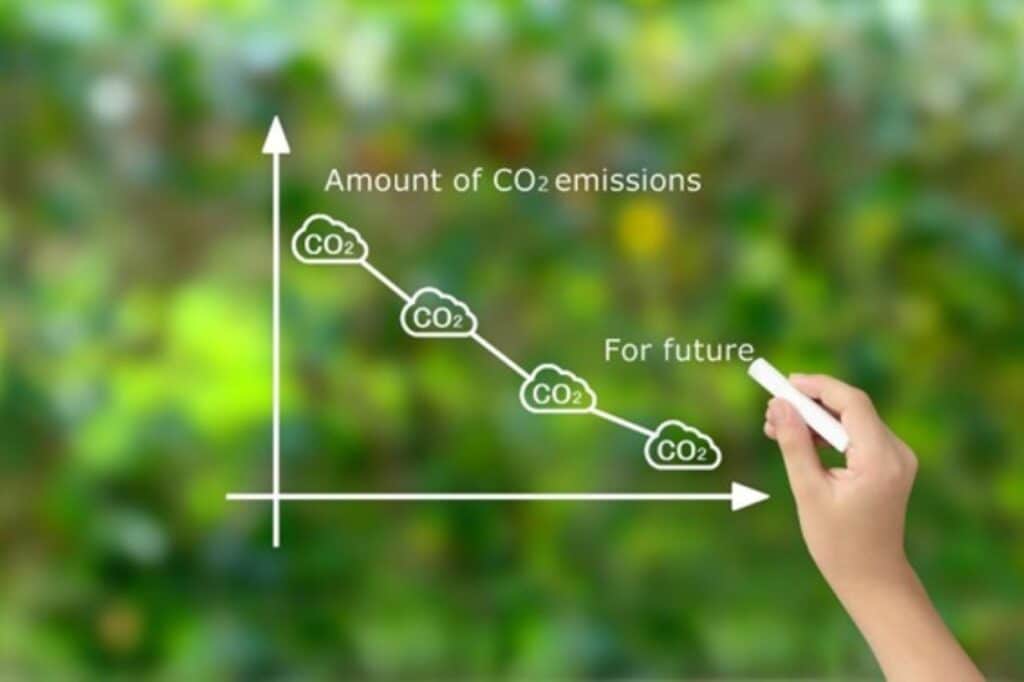
削減実績量は、自社のScope 1(直接排出)・Scope 2(間接排出)を削減した取り組みにより算出される指標です。この削減量は、結果として取引先などのScope 3(他社の間接排出)にも影響しますが、他社のScope 1・2・3排出と相殺する目的では使用できません。
削減実績量とScope 1・2・3の間の主な違いは、Scope 1・2・3は排出源の分類であるのに対して、削減実績量は削減の成果を示す指標という点です。削減実績量は、各企業が連携し、削減努力を重ねるための補完的な情報といえます。
削減実績量を活用するメリットとデメリット
削減実績量を活用する場合には、メリットとデメリットがあることを理解しておかなければなりません。メリットとデメリットそれぞれについて紹介します。
削減実績量のメリット:成果の「見える化」と信頼獲得につながる
削減実績量は、企業の脱炭素施策によって実際に削減できた排出量を、製品単位で示せる指標です。これにより、製品の製造段階における削減効果や、削減のロードマップに沿った取り組みの進捗を「見える化」できます。
また、その成果は外部へのアピール材料にもなり、結果として、環境意識の高い消費者や取引先、投資家などからの信頼性向上につながり、競争力の向上をもたらします。
削減実績量のデメリット:定義の不明確さと算定負担
削減実績量は、削減できた排出量を製品単位で示せるものです。ただし、その定義や算定方法が現時点では統一されていない点がデメリットであるといえます。そのため、企業や業界ごとに算定した数値や評価の基準が均一ではない可能性があり、客観的な比較や信頼性ある評価が難しくなるおそれがあることに注意が必要です。
また、算定にはLCAに関する知見や排出データの整備が不可欠であり、導入には専門的な知識と一定のコスト・手間がかかります。さらに、「削減貢献量」との違いが十分に理解されない場合、両者が混同されて誤解を招く可能性もあるでしょう。
削減実績量を活用して企業の信頼性を高めよう!
削減実績量は、企業の脱炭素施策によって実際に削減できた排出量を、製品単位で示せる指標です。企業のGXへの取り組みを、製品レベルで「見える化」することで、外部へのアピール材料になることが期待できます。削減実績量を活用し、環境意識の高い消費者や取引先、投資家などからの企業への信頼性を高めましょう。
削減実績量の算定には、LCAに関する知見や、排出データの整備が不可欠です。導入には専門的な知識が必要であるため、専門家に相談することをおすすめします。
「e-dash」は、脱炭素への取り組みを総合的にサポートするプラットフォームです。製品単位のCFP算定・分析・報告をワンストップで支援するサービス「e-dash CFP」を提供しておりますので、CFP算定にご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。
以下資料では、CFPの概要から算定の進め方や算定方法について、初めての方にもわかりやすく解説しています。こちらもぜひ参考にしてください。



とは?-1-640x360.png)













