急速に進行している地球温暖化の原因の1つに、二酸化炭素を含めた温室効果ガスの排出量が増加していることが挙げられます。
温室効果ガスの大半は二酸化炭素が占めています。そのため、異常気象や海面上昇をもたらす地球温暖化を止めるには、二酸化炭素の排出量を減らすことが求められているのです。
そこで、この記事では二酸化炭素排出の原因や部門別の排出量、国別のランキングを解説します。
記事の後半では、各国の取り組みについても紹介します。
目次
二酸化炭素排出量と温室効果ガス排出量

二酸化炭素は温室効果ガスの一種であり、地球温暖化の大きな原因であると言われています。その二酸化炭素を各国がどのくらい排出しているのかを示すのが二酸化炭素排出量です。
世界で排出される温室効果ガスのなかで、二酸化炭素は76.0%を占めています。とりわけ、日本では約90%が二酸化炭素であるため、温室効果ガスの大部分は二酸化炭素であることがわかります。
そのため、地球温暖化を防止、すなわち温室効果ガスを削減するには、二酸化炭素の排出量を減らすことが重要です。2015年にはパリ協定にて、二酸化炭素の排出量に関して、各国の削減目標が定められました。
【関連記事】二酸化炭素が増えるとどうなる?影響や原因、世界の取り組みを紹介
二酸化炭素排出量の測定の方法

各国の二酸化炭素排出量は、「生産ベースCO2排出」をもとに測定されています。「生産ベースCO2排出」を求めるには、経済統計で用いられるガソリンや電気・ガスなどの「使用量(活動量)」と「排出係数」を掛け算します。
すなわち、直接CO2の排出量を測定しているわけではないため、正確性を疑問視する声もあります。
例えば、国同士での分業が進む中、先進国の多くが自国にある工場を閉鎖し、新興国へ移転する企業が増加しています。当然、工場を他国に移転すれば、移転した国でCO2が排出されることになるため、自国のCO2排出量は減少するでしょう。
つまり、先進国でのCO2排出量を新興国に押し付ける構図が起きています。
日本の二酸化炭素排出の原因とは?産業別の二酸化炭素排出量ランキング

2020年に日本で排出された二酸化炭素は10億4400万トンです。このうち、電気・熱配分前、すなわち生産者側から見た内訳は、以下の通りです。
| 部門 | 割合 |
| エネルギー転換部門(発電所など) | 40.4% |
| 産業部門(工場など) | 24.3% |
| 運輸部門(自動車など) | 17.0% |
| 非エネルギー起源CO2(製品使用や廃棄物など) | 7.4% |
| 業務その他部門 | 5.5% |
| 家庭部門 | 5.3% |
とくに、エネルギー転換部門にて、多くの二酸化炭素が排出されていることがわかります。
日本の電力は二酸化炭素を多く排出する火力発電所に頼る形になっているため、水力発電や風力発電、太陽光発電などの自然エネルギーを使用した発電方法の普及が求められています。
日本の二酸化炭素排出量年度によるランキング

日本における排出量は全体として減少傾向にあります。具体的には、2013年が13億1800トンだったのに対し、2020年では10億4400万トンにまで減少しており、7年間で20%以上も削減しています。
各部門(電気・熱配分後)においては、前年度(2019年度)と比較すると、産業部門では8.1%、運輸部門では10.2%、業務その他部門では4.7%減少しています。
一方、家庭部門では4.5%増加してしまいました。新型コロナウイルスの感染拡大により、自宅で過ごす時間が増え、電力をはじめとするエネルギーの使用量が増えたことが影響していると考えられています。
より日本の二酸化炭素排出量を削減するためには、各家庭での協力も不可欠になるでしょう。
二酸化炭素排出量の世界ランキング
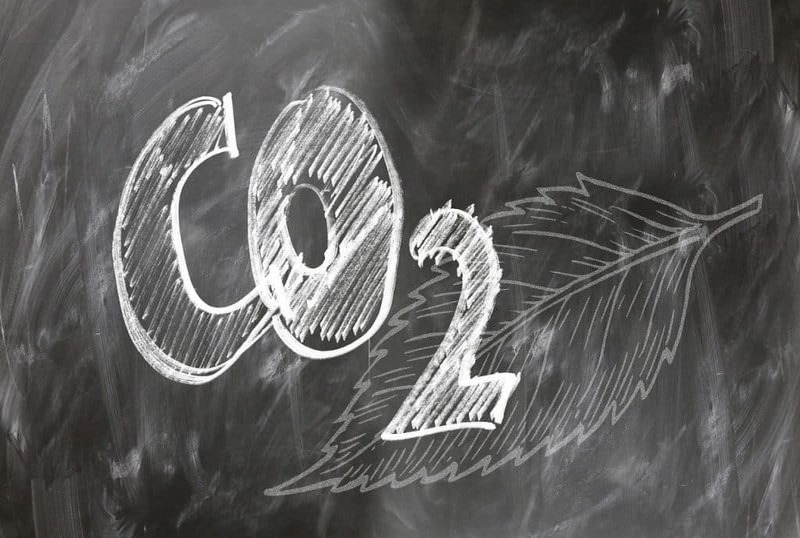
2019年における二酸化炭素排出量のランキングは、以下の通りです。
| 順位 | 国名 | 排出量※単位は100万トン |
| 1 | 中華人民共和国 | 9,882 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 4,744 |
| 3 | インド | 2,310 |
| 4 | ロシア | 1,632 |
| 5 | 日本 | 1,059 |
| 6 | ドイツ | 644 |
| 7 | 大韓民国 | 587 |
| 8 | カナダ | 571 |
| 9 | インドネシア | 584 |
| 10 | メキシコ | 419 |
中華人民共和国やアメリカ合衆国、インド、ロシアといった、面積の大きい国や人口の多い国が上位を占めています。その中で、日本は5位に位置しており、6位以下との数値の差が大きいことから、世界の中でもとくに二酸化炭素の排出量が多い国の1つとして挙げられるでしょう。中華人民共和国やアメリカ合衆国といった大国のみならず、日本でも責任を果たすべく、さまざまな施策に取り組むことが必要です。
【関連記事】世界の気候変動の実態とは?気候変動が日本に与える影響も解説
二酸化炭素排出削減に向けた世界的な取り組み

世界では二酸化炭素排出削減に向けて、数々の取り組みが行われています。中でも、よく知られているのが京都議定書とパリ協定です。
1997年、気候変動枠組条約の締結国が毎年行う会議(COP)の3回目、COP3が京都で開かれた際に、初めて国際的に二酸化炭素排出量の削減目標及び手法が合意されました。その合意が記されているのが「京都議定書」です。
京都議定書では、アメリカ合衆国やEU、日本などの先進国における目標が決められました。しかし、当時新興国であった中国が対象外であったり、アメリカ合衆国が途中で離脱したため、合意の効果に疑問が生じていました。
そこでCOP21で採択したのが「パリ協定」です。パリ協定では、世界共通の目標が決められたほか、190以上の国と地域が参加し、具体的な目標を策定することができました。以降、各国は自国の目標を果たすべく、取り組みが行われています。
【関連記事】地球温暖化対策とは?世界で行われる取り組みをわかりやすく解説
脱炭素社会の実現に向けて企業と個人の取り組みが重要となる

二酸化炭素の排出量削減は、環境問題の中でも大きなトピックであり、世界中で取り組みが進められています。近年は、成果が出始めているため、日本をはじめ多くの国で二酸化炭素の排出量を削減できているのです。
しかし、地球環境を正常に戻すにはまだまだ多くの取り組みが必要であり、国だけの力では限界があります。企業でも個人でもできる協力を行うことが、環境問題の解決に重要です。
CO2の排出をはじめとした脱炭素に向けた取り組みに興味のある企業は、ぜひe-dashにお問い合わせください。












