取引制度とは?.png)
気候変動問題の解決には、温室効果ガスの排出削減が重要な課題です。その一環として「排出量取引制度」が注目されています。この制度はカーボンオフセットとともに、企業が環境負荷を低減するための有効な仕組みです。具体的にはどのように効果的かを解説していきます。
目次
排出量取引制度とは?
排出量取引制度は、定められた温室効果ガスの排出量を企業などが取引できる制度です。排出権取引制度とも呼ばれ、温室効果ガスの排出量を管理し削減を促すことを目的としています。
企業ごとに排出量を定め、余った枠は販売でき、足りない枠は購入しなければなりません。そのため、全体の排出量を効率的に管理でき、削減努力をするほど経済的なメリットを得られます。
日本では2026年からCO2の直接排出量10万トン以上の企業を対象に、全国的な排出量取引制度を導入予定です。現在は、東京都と埼玉県で取り組みが進められています。
排出量取引制度の2つの方式
排出量取引制度には、「キャップ・アンド・トレード方式」と「ベースライン・アンド・クレジット方式」の2つの方式があります。前者は政府が企業ごとに排出枠(キャップ)を設定し、余剰分や不足分を市場で取引する制度です。
一方後者の、「ベースライン・アンド・クレジット方式」は、温室効果ガスの削減に取り組まない場合の排出量(ベースライン)を基準とした自主的な取引を行う制度です。削減に取り組んだ結果、排出量がベースラインを下回った場合、削減分をクレジットとして発行し取引できます。
| 【国内での取り組み例】 「キャップ・アンド・トレード方式」 ・温室効果ガス排出量削減義務(東京都) ・排出量取引制度(東京都) ・目標設定型排出量取引制度(埼玉県) 「ベースライン・アンド・クレジット方式」 ・Jクレジット制度 |
排出量取引制度で得られる3つのメリット

次に、排出量取引制度を利用することで、どのようなメリットがあるかについて解説します。
CO2の削減コストを最小化できる
排出量取引制度を利用することで、温室効果ガス排出のコストを最小限に抑えられます。たとえば、CO2排出を削減できる部門・削減が難しい部門それぞれにおいて、削減できる部門では削減努力を徹底し、削減が厳しい部門では削減枠の購入が可能です。その結果、企業内でも調整が行えるため、コストの削減につながります。
目標を達成しやすい
温室効果ガス排出量の削減目標を決定できるため、企業や国ごとの方針が立てやすい点もメリットの一つです。温室効果ガスの排出削減は、自社の事業内容や活動量、景気の動向を考慮しながら判断できるため、目標に向けて柔軟に対応しやすい傾向があります。
CO2の削減方法を自由に選べる
排出量削減の方法は自由に選べるため、どの企業にとっても取り組みやすいといえるでしょう。自社で温室効果ガス排出量を削減する、排出枠を購入して補うなど、企業の状況や経営方針に応じた方法で排出量削減に貢献できます。
排出量取引制度における3つのデメリット
排出量取引制度にはメリットがある一方で、課題も存在します。どのような点がデメリットなのか見ていきましょう。
業界や部門によっては設定が難しい
排出量取引では、業界・部門によっては排出枠の設定は簡単ではありません。排出枠が増え、売り手が多くなってしまうと排出枠が安価で取引されてしまいます。一方で、排出枠が少なくなると、コストがかかり企業の負担につながる可能性があります。
また、景気変動・省エネ対策などによって排出枠の需要が変動することなども、設定が難しくなる原因です。
カーボンリーケージのリスクが高い
排出量取引制度が導入されると、企業は排出枠の購入や脱炭素化への投資が必要となり、生産コストが上昇します。その結果、規制の緩い国へ事業拠点の移転が進むことで起こる国内の雇用や経済への影響が懸念されます。また、移転先で排出削減対策が不十分な場合、世界全体のCO2排出量がむしろ増える可能性があります。
そのため、カーボンリーケージ(炭素漏れ)を防ぐために、リスクの恐れがある企業などに対しては、排出枠を多めに配分するなどの対策が必要です。
| ■カーボンリーケージとは? カーボンリーケージとは、企業が規制の回避やコスト削減のために比較的規制の緩い国に移転する現象のこと。地球全体でみると排出量が増加する可能性があり、炭素リーケージや炭素漏出ともいわれます。 |
「原単位」の目標が多い
「原単位目標」は、生産物の1単位あたりに排出するCO2排出量を削減する目標のことです。単位あたりのCO2排出量削減ばかりを意識したとしても、全体の生産量をコントロールしなければ、結果的にCO2の総排出量が増えてしまう可能性があります。
結果として、排出権取引での本来の目的である「CO2の排出量を減らす」ことができない可能性があるため、デメリットの一つといえるでしょう。
排出量取引制度の流れ
排出量取引制度は、削減目標の設定から取引枠・量の確認まで複数のステップで構成されます。ここでは、全体の流れを見ていきましょう。

STEP1.目標を設定する
温室効果ガスの排出枠を決めるために、目標を設定します。具体的には、「○年に対して温室効果ガス排出量を○%削減する」と決めることです。基準年の数値からどのくらい削減するのかという考えのもと、排出枠を決定します。国や部門での大きな枠組みで排出枠を決定してから、企業や事務所などに分配し、実行する流れです。
STEP2.分配方法を決定する
| 排出量の分配方法 | 概要 |
| グランドファザリング方式 (無償) | 企業や施設の過去の排出量に基づき排出枠を決定 |
| ベンチマーク方式 (無償) | 単位重量あたりの生産物を製造するときに望ましい排出量(ベンチマーク)を定め、生産量に応じて排出枠を決定 |
| オークション方式 (有償) | オークションで企業や施設などが排出枠を購入 |
グランドファザリング方式
企業や施設に対して特定の年・期間にどれだけの温室効果ガスを排出したのかを調べます。その排出量に応じて、排出枠を無償で交付します。
ベンチマーク方式
単位重量あたりの生産物を製造するときに望ましい温室効果ガス排出量(ベンチマーク)を定め、排出枠を決定します。企業や施設の生産物・技術などの過去に取り組んだ排出量削減努力に応じて定める流れです。
オークション方式
オークションで企業や施設などが排出枠を購入する方法です。入札によって排出枠を得る方法となるため、有償で排出枠を獲得できます。(オークション方式以外では、無償で排出枠を交付してもらえます。)
STEP3.取引を実施する
企業や施設が温室効果ガス排出の削減努力を行った結果、排出量に差異が生じます。削減するために努力したものの削減量が足りなかったときや、努力して排出枠が余ったときに排出量取引が行えるのです。削減量が足りない場合は排出枠を購入し、余裕が生まれた場合は排出枠を売りに出すというトレードが行われます。
STEP4.取引枠・量を確認する
一定期間を経て、どれくらいの排出量となったのか調査をします。定められている排出枠に対し、削減努力が行われたかを確認しなくてはなりません。排出枠よりも実際の排出量が少なければ、削減努力をしていたことが分かりますが、排出枠を超えてしまった場合、罰則が科せられます。
海外の排出量取引事情
| EU | 産業界・航空業界・海運業を対象とする、世界最大の排出量取引市場で排出量を管理 |
| アメリカ・カリフォルニア州 | 独自の制度を運用し、企業に対して厳格な排出規制がされている |
排出量取引制度は世界各国でも導入が進められており、先行事例から学べる点も多くあります。ここでは、海外の情勢について紹介します。
EU
EUは世界最大の排出量取引市場を運営し、産業界や航空業界を含む幅広い分野で排出量を管理しています。EUの排出量取引制度では企業ごとに排出上限が設定されるため、不足分は市場で取引が可能です。排出削減を促す仕組みとして高く評価されており、企業の環境対策や技術革新を後押ししています。
またEUの取り組みは、経済全体の低炭素化を推進する役割を担っていることも覚えておきましょう。
アメリカ・カリフォルニア州
カリフォルニア州は、独自の温室効果ガス削減制度を運用し、企業に対して厳格な排出規制を実施しています。全米初の「地球温暖化対策法」に基づいて排出量取引制度を導入。排出権の売買を通じた削減を促進しています。
さらに、カナダのケベック州との連携により、北米全体の排出削減にも貢献。持続可能な経済成長と環境対策を両立するモデルとして注目されています。
排出量取引制度に関する日本国内での取り組み事例をご紹介!
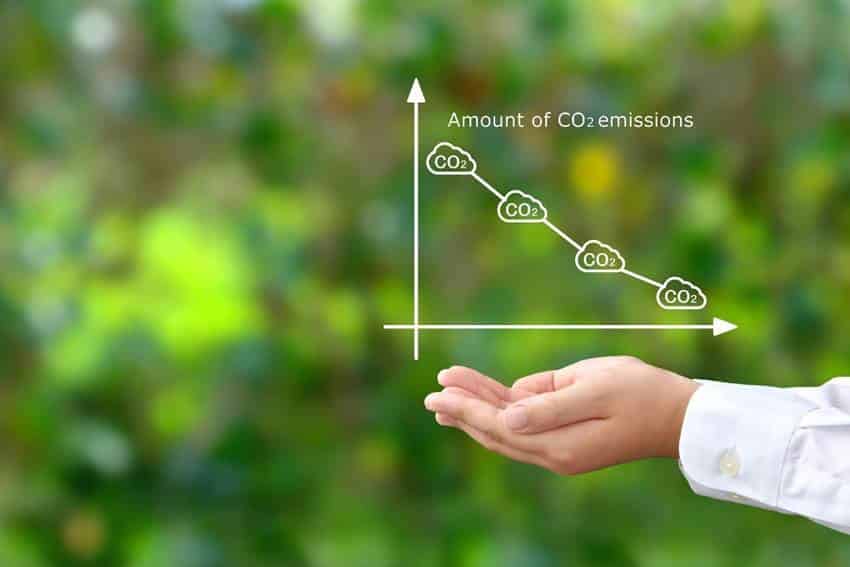
世界と比較してみても、まだまだ日本の取り組みは十分とはいえません。政府・さまざまな企業や団体のなかでも、先行した取り組みを行っている事例があるのでご紹介します。
東京都:「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」
東京都では、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を2010年4月に導入しています。この制度は、主に大規模事業者に対して次のような内容を求めています。
| 【温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度】 ・CO2排出量の算定をする ・第三者審査機関により検証を行う ・CO2排出量の削減 |
また、2020年~2024年度を第三計画期間として、「2020年までに2000年比の25%、CO2を削減」する目標を設定し、現在でも続けています。
埼玉県:「目標設定型排出量取引制度」
埼玉県では、「目標設定型排出量取引制度」を導入しています。大規模事業者を対象に、目標削減率を5年間で達成することを求める内容です。主に、「2020年までに2005年比の21%、CO2を削減する」設定をしています。東京都と同様、2020年~2024年度の第三計画期間としての導入です。
GXリーグの排出量取引制度「GX-ETS」
GXリーグとはカーボンニュートラルの実現に向けて、GX(グリーン・トランスフォーメーション)に取り組む企業群が官・学とともに連携し協働する場です。
GX-ETSは、GXリーグに参加する企業が自主的にCO2排出量を取引する制度です。2023年から試行運用が開始され、2026年度から主に大規模排出事業者に対して参加の義務化が検討されており、本格的な稼働が予定されています。企業は毎年度自らのCO2の直接排出量を算定し、これと等量の排出枠の償却を行うことが求められます。
排出量取引制度に向けて企業が今からできる準備
脱炭素化が加速するなか、企業が将来的な排出量取引制度に備えるには自社のCO2排出量を正確に把握し、排出量削減のために省エネ・再エネ設備の導入を検討する必要があります。さらにカーボンクレジットを活用することで、効率的に排出削減枠の埋め合わせ・償却が可能です。
早期に準備を行えば競争力向上につながり、持続可能な経営の実現に寄与するでしょう。排出量取引制度に向けた準備は以下の3点です。
自社のCO2排出量を正確に把握する
| 環境省「サプライチェーン排出量算定ガイドライン」 ・企業がサプライチェーン全体のCO2排出量を算定するための方法や手順を解説 ・CO2排出量の正確な把握に役立つ 事業者向けCO2削減のための自己診断ガイドライン ・事業者がCO2排出状況を自己診断する手順を解説 ・データ収集の仕組みづくりに役立つ |
省エネ・再エネ設備を導入する
| 経済産業省「省エネポータルサイト」 ・省エネに関する最新の政策、支援策、導入事例を閲覧可能 ・CO2削減努力で取引の負担を減らす 脱炭素ポータル「企業の方へ」 ・企業向けの脱炭素化支援情報や事例を解説 ・効果的な削減策検討に役立つ |
カーボンクレジットを活用する
| Jクレジット公式サイト ・制度の概要や活用方法、参加手続きなどを詳しく解説 ・国が認証する制度のため、導入しやすい |
CO2排出量の可視化から!e-dashのサービス紹介
CO2排出量の可視化は、効果的な削減対策の第一歩です。ここでは、CO2排出量の見える化から削減まで支援する「e-dash」のサービスについてご紹介します。
企業のCO2排出量の見える化を支援
e-dashは、企業のCO2排出量の可視化を支援しています。Scope 1・2の算定は、電気やガスの請求書をクラウド上にアップロードするだけ。専門知識・経験がない方でも、手間なく簡単、そして正確にCO2排出量の算定・見える化が可能です。データ収集や算定方法が煩雑なScope 3算定にはコンサルティング支援も用意しています。
CO2排出量の削減やカーボンクレジットの購入も一気通貫で支援
e-dashではお客様の現状や目標に応じて、様々なメニューの中から最適な削減プランを提案し、施策実行からその後のモニタリングまで丁寧に伴走支援を行います。
さらにオンラインで簡単にカーボンクレジットを購入できるマーケットプレイス「e-dash Carbon Offset」も提供しています。マーケットプレイスを活用し、柔軟かつ効率的な排出量調整を実現していきましょう。
排出量取引制度に向き合うために

排出量取引制度には、上記で記載したデメリットのような課題もあります。課題と向き合うためには、まず、国や企業がどれくらい地球環境に対して目を向けるかを把握する必要があります。排出量取引制度に頼りすぎてしまえば、新たな技術開発は行えない可能性もあるものの、現状のままでは今よりも一層深刻な環境破壊につながるでしょう。そのため、「地球温暖化の抑制」を達成するためにも、課題と向き合っていきながら制度に取り組んでいくことが大切です。
弊社の「e-dash」は、「脱炭素を加速する」をミッションとして掲げています。クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援を行っています。
脱炭素に関するお悩み・課題はぜひe-dashにご相談ください。





をわかりやすく解説!企業が知っておくべき影響と対応策-1.png)







