
脱炭素社会への移行が加速する今、省エネなどの企業の温室効果ガス排出量を削減する取り組みにおいて、「環境価値」の理解と活用は重要な要素となっています。
本記事では環境価値の基本から、制度の仕組み、証書の種類、メリットまでをわかりやすく解説します。
目次
環境価値とは?

環境価値とは、再生可能エネルギーやその他の非化石電源が持つ「温室効果ガスを排出しない」という環境面での付加価値を指します。
再生可能エネルギー由来の電力や原子力発電から供給される電力は、通常の電力と同じ機能を持ちます。しかし、環境負荷が小さいという点で通常の電力と区別されます。
日本では、この環境価値を「グリーン電力証書」「非化石証書」「J-クレジット」などの形で切り離し取引可能な制度を発足させています。
環境価値が注目される背景
2015年にフランス・パリで開催されたCOP21では、全ての締結国が温室効果ガスの排出削減に取り組むことを定めたパリ協定が採択されました。同年の国連サミットでは、持続可能な開発目標(SDGs)が採択され、気候変動や社会課題への関心の高まりを背景にESG投資への注目も世界的に高まっています。
こうした国際的な動きを受けて、企業には排出削減の取り組みが強く求められるようになり、再生可能エネルギーの導入や環境価値の活用が重要な手段として位置づけられています。
日本で活用できる主な環境価値の種類
| グリーン電力証書 | 非化石証書 | J-クレジット | |
| 概要 | 再生可能エネルギー由来の電力の環境価値を証書化したもの | 化石燃料(石油や石炭など)を使用せずに発電した電力の環境価値を証書化したもの | 温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして認証するもの |
| 発行主体 | 証書発行事業者(第三者機関) | 発電事業者及び電力広域的運営推進機関(政府が認証) | 政府 |
| 対象 | ・再生可能エネルギーによる発電 | ・再生可能エネルギーによる発電 ・原子力発電(※非FITのみ) | ・省エネルギー設備の導入(高効率機器など) ・再生可能エネルギーの導入(太陽光など) ・燃料転換や廃棄物処理改善による排出削減 ・森林管理や植林などによる吸収量の創出 |
| 購入方法 | 証書発行事業者から購入 | JPEX(日本卸電力取引所)でのオークション | 入札・保有者や仲介事業者から購入 |
| メリット | マークの利用により取り組みをアピール可能 | 取引市場が大きく価格が安定している | 相対取引で販売することも可能 |
日本において取引できる主な環境価値にはグリーン電力証書、非化石証書、J-クレジットなどがあります。非化石証書やグリーン電力証書は、電力が再生可能エネルギーや非化石エネルギー由来であることを示す「環境価値」を証明するものです。一方、J-クレジットは、温室効果ガスの排出削減や吸収の成果をクレジットとして取引可能にする制度です。それぞれの仕組みを解説します。
グリーン電力証書
グリーン電力証書は、再生可能エネルギーによって発電された電力の「環境価値」を切り離し証書化したものです。対象は、主に太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱などを用いて発電された電力です。発電した電力量をもとに発行され、購入者は環境に負荷の少ない電力を使ったとみなされます。
グリーン電力証書は、証書発行事業者によって発行され、その環境価値は、一般財団法人日本品質保証機構によって認証されています。さらに、一定の条件を満たせば温対法に基づく温室効果ガス排出量の報告に活用することも可能です。
証書を購入することで、グリーン電力の利用を示す「グリーン・エネルギー・マーク」などのマークが使用できるため、地球温暖化対策への貢献を社外にアピールできる点もメリットです。
|
■グリーン・エネルギー・マークとは? グリーン・エネルギー・マークは、製品の製造などに使用した電力が再生可能エネルギーであることを示すシンボルです。企業はこのマークを製品や広告に表示することで、環境配慮の姿勢をPRできます。2008年に制定され、消費者の信頼や製品の差別化、SDGs・ESGへの対応にも活用されています。 |
非化石証書
非化石証書とは、再生可能エネルギーや原子力などの非化石電源から発電された電力に由来する環境価値を証書化し、取引可能にしたものです。非化石電源は、化石電源と比較して温室効果ガスの排出量が少ない、またはゼロであることから環境負荷が小さいとされています。
非化石証書はFIT非化石証書、非FIT非化石証書(再エネ指定)、非FIT非化石証書(再エネ指定なし)の3種類があります。
FIT非化石証書は固定価格買い取り制度の適用を受ける電源の証書であり、最低入札価格が固定されています。非FIT非化石証書は相対取引の場合、最低・最高価格の設定がありません。
企業はこの非化石証書を購入することで、自社の使用電力を非化石電源により賄ったとみなされ、温室効果ガス排出量の報告や削減目標に反映ができます。
非化石証書は他の環境価値と比較して取引市場が大きく価格が安定しているのがメリットです。また電力とセットになっている取引形態のものもあるため導入しやすいのも特徴です。
J-クレジット
J-クレジットは、温室効果ガスの排出削減・吸収した量を「クレジット」として、政府が認証・発行し、購入・売却できるようにした制度です。省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用などによる温室効果ガスの削減量だけでなく、森林の適切な保全・管理などの温室効果ガス吸収量も価値化されています。
企業がJ-クレジットを購入すると、そのクレジットを用いて自社の温室効果ガスをカーボンオフセットできます。カーボンオフセットとは、自社内で削減努力をしてもなお削減が難しい温室効果ガスをクレジット購入することでオフセット(埋め合わせ)し、実質的な排出量をゼロに近づける仕組みです。
クレジットの創出者は企業や自治体、農林業者など多岐に渡り、企業間だけでなく地域全体でカーボンオフセットやカーボンニュートラルに取り組めるというメリットがあります。
J-クレジットは主に相対取引されており、近年は需要の高まりを背景に価格・取引量ともに増加傾向にあります。
国際イニシアチブとの関係
ここでは、日本における環境価値に関する証書および制度が国際イニシアチブにどのように対応しているのか、解説しています。
以下は日本の証書およびクレジット制度の国際イニシアチブとの対応表です。
| グリーン電力証書 | 非化石証書 | 再エネ電力由来のJ-クレジット | 再エネ熱由来のJ-クレジット | |
| CDP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SBT | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RE100 ※ | ○ | FIT非化石証書のみ | ○ | – (熱は RE100 の対象外) |
参考:経済産業省「国際的な気候変動イニシアチブへの対応に関する ガイダンス」
※調達する再エネ電力については、「運転開始またはリパワリング(古い設備を更新し、出力を増強すること)から15年を超えた発電設備によるものを除く」といった独自の基準が設けられています。
CDP、SBT、RE100 はすべて温室効果ガス削減の取り組みを評価する国際的なイニシアチブです。
グリーン電力証書は、3つのイニシアチブすべてにおいて温室効果ガス削減の取り組みとして報告に使用できます。
非化石証書も同様に、3つのイニシアチブすべてにおいて温室効果ガス削減の取り組みとして報告に使用することが可能です。ただしRE100において、非化石証書のうち対象となるのは政府によるトラッキングFIT非化石証書などに限定されます。
再生可能エネルギー由来のJ-クレジットについては、再エネ調達量として報告に活用できます。
ただし、J-クレジットの単位である「t-CO2」は温室効果ガス算定の国際的な基準であるGHGプロトコルにおいては、そのまま温室効果ガスの削減量としてカウントすることはできません。この点で、J-クレジットは削減の定量的評価には直接使用できず、再エネ調達量として位置づけられます。また、CDP・SBTでは再エネ電力・再エネ熱由来、RE100では再エネ電力由来のJ-クレジットを対象としているため、用途によって注意が必要です。
環境価値の取引の方法

環境価値の取引の方法は主に上記の3つです。それぞれ解説します。
環境証書・クレジットを購入する
現在、グリーン電力証書とJ-クレジットは発行主体、保有者、仲介者などから購入が可能です。非化石証書のうちFIT非化石証書は一般企業も購入できますが、非FIT非化石証書については、小売電気事業者以外は購入できません。
環境価値取引の導入に最もハードルが低い方法と言えますが、再生可能エネルギー発電設備の設置をしたほうが追加性という点で環境貢献度が大きいと評価される国際的な風潮があるため、要件に合わせてよく考える必要があります。
環境価値がセットになった電力メニューを導入する
環境価値がセットになった再エネ電力メニューを選択すれば、証書の個別手配が不要なため、手軽に導入可能です。電力使用量全体を対象とするプランであれば、環境価値の調達量計算などの煩雑な業務も不要です。ただし、証書の種類やトラッキング方式など、電力メニューの内容を十分に確認した上で選択することが重要です。
コーポレートPPAを導入する
コーポレートPPAとは発電事業者とPPA(電力購入契約)を結ぶことで再生可能エネルギー発電設備が生み出した電力を使用する方法です。発電事業者と契約した企業は、発電設備の使用料や電気料金とともに環境価値を購入し活用することができます。
PPAは主に、オンサイトPPAとオフサイトPPAの2種類があります。オンサイトPPAでは、企業の敷地内に発電事業者が太陽光発電などの設備を設置し、発電された電力を企業が直接自家消費します。一方、オフサイトPPAは、発電事業者が敷地外に保有する再エネ設備で発電した電力を、電力系統を介して企業に供給する形態です。
オフサイトPPAの中にはバーチャルPPAという取引の形態があります。これは企業が再生可能エネルギーの電力を物理的に受け取ることなく、環境価値だけを取引する契約です。企業は発電事業者と長期の契約を結び、環境価値の購入と電力の市場との価格差のみを負担します。
小売電気事業者を通じて契約し価格差の負担もしない取引形態も存在します。
バーチャルPPAは既存の電力契約を維持しながら環境価値の取引が行える方法として注目されています。
企業が環境価値を購入するメリット
ここでは企業が環境価値を購入する具体的なメリット3つについて解説します。
国際イニシアチブに対応できる
環境価値を取り入れることで、企業はCDP、SBT、RE100などの国際的なイニシアチブの求める要件に一部対応することが可能です。
ただし、これらのイニシアチブでは、再生可能エネルギー由来の電力利用や温室効果ガス削減の「根拠の明確な実績」が重要視されており、証書の種類や調達方法によって認められるかどうかが異なります。
たとえばRE100では、トラッキング付きのFIT非化石証書や、電力とセットで環境価値を調達する契約形態(相対契約等)のみが再エネ調達手段として認められるため、購入する証書の選定には注意が必要です。
取引先の要望に応えられる
取引先から再エネ電力の利用や温室効果ガス排出量の削減を求められるケースが増えており、環境価値の購入はこうした要請に応える手段として有効です。とくに、大手企業との取引においては、再エネ利用の証明が調達条件となることもあり、証書の活用がパートナーシップの維持・拡大につながります。
設備投資などを行わずに温室効果ガス排出量を実質的に削減できる
環境価値の購入は、自社の削減努力だけでは対応が難しい領域に対し、オフセット手段として活用できる取り組みです。とくに製造業などでは、設備更新を伴わずに一部の排出量を補完的にカバーする方法として有効です。制度によっては、証書の活用のみでも取り組みとして認められるケースがありますが、可能な範囲で自社の削減努力と併用することで、より信頼性の高い対応が期待されます。
環境価値の課題

環境価値の制度は、グリーン電力証書、非化石証書、J-クレジット、など複数の制度が併存しており、それぞれで申請手続きや要件が異なるため、全体像をつかみにくいという難しさがあります。
とくに中小企業にとっては、制度の理解、制度間の比較、市場動向の把握といった幅広い知識が求められるため、取り組む上での負担が大きくなりがちです。
環境価値を適切に活用するには、制度の仕組みを十分に理解し、事前準備を進めることが重要です。そのため、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
環境価値に関するご相談は「e-dash」へ
企業が環境価値を購入すると、国際イニシアチブへの対応、企業としてのアピール、設備投資などを行わずに温室効果ガス排出量を実質削減できるなどのメリットがあります。この機会に環境価値の取引について検討してみてはいかがでしょうか。
弊社の「e-dash」では、非化石証書の購入支援やカーボンクレジットのマーケットプレイスの運営を行っています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
また、以下資料では非化石証書について、より詳しく解説しています。こちらもぜひご参考ください。
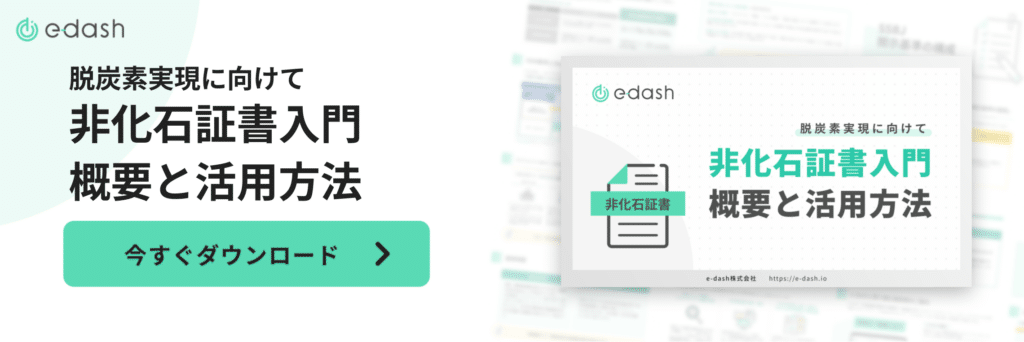


とは?-1-640x360.png)












